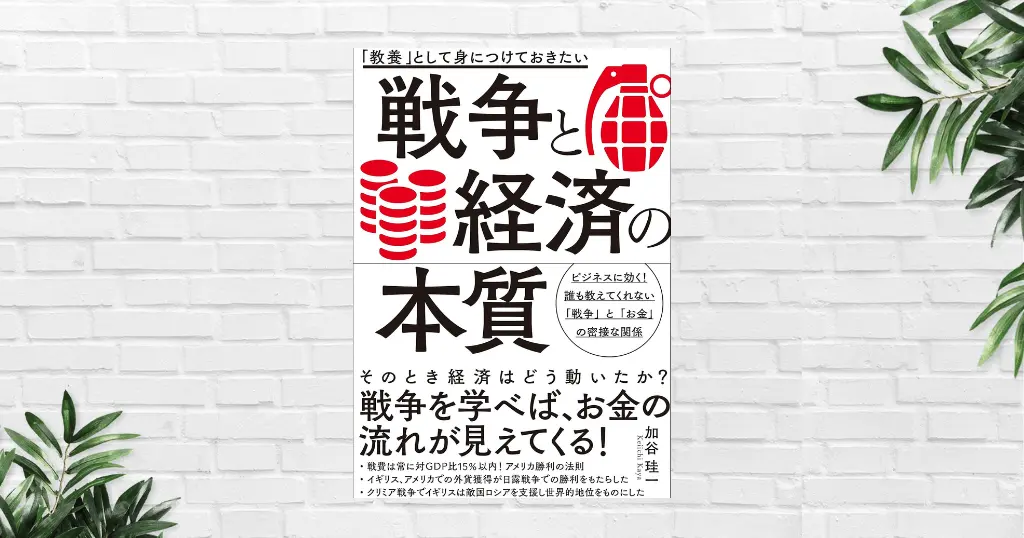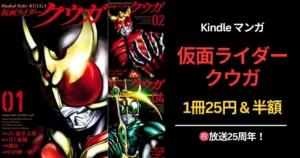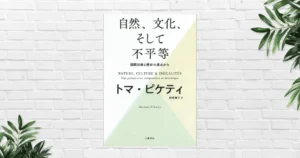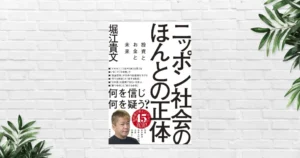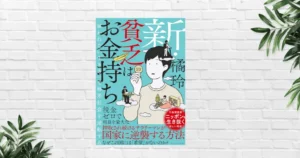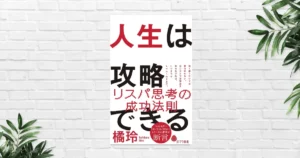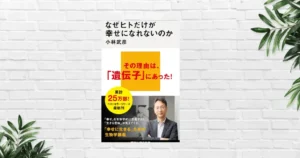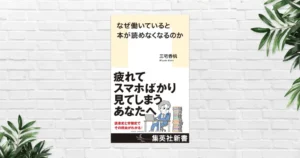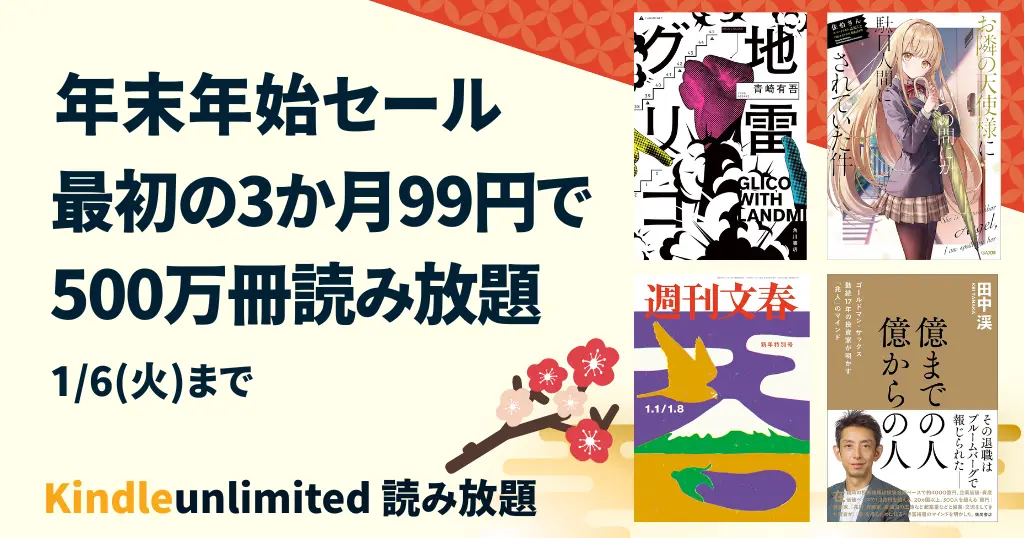- 戦争の本質は「お金・経済」
軍事費は国力そのもので、戦争は「お金の動き」で決まる。戦費調達は国債発行につながり、インフレや経済破綻を招く。 - 戦争と景気・株価の関係
戦争は経済を破壊する一方、新産業需要を生み景気刺激にもなる。朝鮮戦争特需は日本復興の起爆剤となった。 - 現代の戦争は技術と金融
地政学に加え、AI・半導体・金融システムを握る国が覇権を取る。戦争と経済の理解は現代を生きる必須の教養。
★★★★☆
『「教養」として身につけておきたい 戦争と経済の本質』ってどんな本?
戦争は多くの犠牲を伴うため、誰もが避けたいと願うものです。
特に原爆を経験した日本人にとって「戦争は二度と起こしてはならない」という思いは強いでしょう。
しかし現実には、世界のどこかで常に戦争が起こり続けています。
なぜ戦争は繰り返されるのか?
加谷珪一さんの『「教養」として身につけておきたい 戦争と経済の本質』は、その問いに「経済」という切り口から迫った一冊です。戦争の背後にある経済の論理を、歴史と現代の事例を交えながら解き明かします。
結論を先に言えば——
戦争の本質は「お金の動き」であり、国力(経済力)が戦争の行方を決める ということです。
本書は、時事的なトピックを超えて歴史的・構造的な理解を与えてくれます。
戦争と経済は「表裏一体」
歴史を振り返ると、戦争は単なる領土や宗教の対立ではなく、多くの場合「経済的利益」の衝突が引き金になっています。例えば、第一次世界大戦は列強の植民地支配や資源獲得競争の延長線上にあり、第二次世界大戦も世界恐慌を経たブロック経済体制の中で勃発しました。
現代の戦争も、天然資源・エネルギー・市場支配を巡る争いが根底にあります。ウクライナをめぐるロシアの動きも、単なる民族主義ではなく「エネルギー供給ルートと安全保障」が背景にあります。
戦争と 国力・経済・株価
戦争には莫大なコストがかかります。軍事費を賄うには国家の経済力が不可欠であり、結局のところ「戦争の現実=お金」だと加谷さんは指摘します。
軍事費と国力──「戦争経済」と国家財政
- 平時の軍事費
- 各国の軍事費はGDP比で1~3%が一般的。米国は3.5%、中国は2.1%、日本やドイツは1.0%程度にとどまる。
- 米国の軍事費は年間70兆円超、日本の国家予算100兆円と比較すると、その巨額さがわかる。
- 有事の軍事費
- 戦争が始まれば軍事費は桁違いに膨張
- 日清戦争:GDP比0.17倍
- 日露戦争:GDP比0.6倍
- 太平洋戦争:GDP比8.8倍 - 太平洋戦争が「国力を無視した無謀な戦争」であったことが、数字からも明らか
- 戦争が始まれば軍事費は桁違いに膨張
- 戦費調達の現実
- 多くの場合、戦争は国債発行で賄われる
- 太平洋戦争では日銀の直接引き受けによって国債が発行。戦後にはハイパーインフレと預金封鎖を招いた。
戦争とマクロ経済──国債、金利、インフレ
戦費を国債で調達すれば、必然的に金利は上昇し、投資は冷え込みます。中央銀行が国債を大量に引き受ければ、通貨供給が膨張しインフレが加速します。日本は太平洋戦争後にデフォルト、ハイパーインフレ、預金封鎖を経験しました。
つまり戦争は、「国の信用を壊し、経済を破壊する行為」に他なりません。
戦争と株価──「表面的な安定」と「反動」

意外にも、太平洋戦争期の日本株価は比較的安定していました。これは国家総動員体制下で株価を人為的に支えたからです。しかし戦後、反動不況が一気に襲いました。
日本経済を救ったのは、皮肉にも「朝鮮戦争特需」でした。米軍の前線補給基地として日本に膨大な発注が流れ込み、日本企業は息を吹き返しました。ここから高度経済成長が始まったのです。つまり日本は「戦争の恩恵」を受けて復興を遂げた面もあるという、複雑な歴史を持ちます。
📊 【参考】日本経済の「上昇と停滞」サイクル

日本経済は 「上昇期」と「停滞期」を繰り返す波」 の歴史を歩んできました。
| 区分 | 時期 | 年代 | 期間 | 状態 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 日本経済黎明期(明治) | 1880〜1920 | 約40年 | 上昇 | 近代産業の確立・急成長 |
| B | 長期低迷期(昭和戦前) | 1920〜1945 | 約25年 | 停滞 | 世界恐慌・戦争による経済停滞 |
| C | 戦後高度成長期 | 1945〜1960 | 約15年 | 上昇 | 朝鮮戦争特需・輸出拡大・復興 |
| D | 停滞期 | 1960〜1975 | 約15年 | 停滞 | 石油ショック・インフレ |
| E | バブル経済期 | 1975〜1990 | 約20年 | 上昇 | 地価・株価の異常高騰 |
| F | 長期低迷期(平成) | 1990〜2008 | 約20年 | 停滞 | バブル崩壊・「失われた20年」 |
| G | 平成バブル~ | 2008〜現在 | 15年以上 | 上昇 | 金融緩和・株価回復・資産高 |
⏩ ポイントまとめ
- 現在は、アベノミクス以降、上昇期にあるが、その持続性は不透明。
- 日本経済は 「上昇期」と「停滞期」を約15〜25年周期で繰り返している。
- 上昇期には技術革新・戦争特需・金融緩和など「外部要因」が大きな役割を果たす。
- 停滞期は戦争・世界的ショック・バブル崩壊など「リセット」が起こる。
📌別次元の国家サイクル論も参考に
🔗国家は50年周期で栄枯盛衰を繰り返す(算命学)~日本の国家サイクルを知り、投資・人生に活かす
戦争とビジネス──ここに「戦争の本質」がある
1776年建国のアメリカは、歴史の浅い新興国でした。しかし第一次世界大戦において、ヨーロッパ諸国が甚大な犠牲を払う中で、アメリカは本土が傷つくことなく「戦争ビジネス」で巨額の利益を得ました。その富を基盤に、アメリカは世界覇権国への階段を駆け上がったのです。
戦争は倫理的に否定されるべきものですが、経済的には一部の国家や企業に巨大利益をもたらしてきました。
ここに「戦争の本質」があります。
経済制裁は「戦争の延長」
近年は、武力による直接的な戦争だけでなく、経済制裁や金融システムからの排除(例:SWIFT排除)が「武器」として使われるケースが増えています。経済制裁は国家に深刻なダメージを与える点で、戦争と同じ効果を持ちます。
この視点から見ると、国際関係は「軍事力」+「経済力」=「総合的な戦争力」で決まることが理解できます。
戦争は「イノベーション」と「経済発展」を促す
皮肉なことに、戦争は科学技術の大きな発展を促してきました。インターネットやGPS、ジェット機など、現代文明を支える多くの技術が戦争から派生しています。また、大規模な戦時動員によって産業構造が変化し、結果的に経済の生産力が高まることもあります。
ただし、その発展の代償として膨大な犠牲を払う点を忘れてはなりません。
グローバル経済と「新しい戦争」
かつて戦争の勝敗を決めたのは地理条件でした。しかし現代では、テクノロジーと金融システムを制した国が勝つ時代に移っています。
AI、サイバー攻撃、半導体、金融ネットワーク──
「非軍事的な戦争」をを押さえる国が、次世代の覇権を握ります。非中央集権的なビットコイン市場も金融封鎖対策の一つです。また、米中対立はまさに「新しい経済戦争」の典型です。
まとめ:個人にとっての意味──戦争と私たちの生活
戦争は遠い世界の出来事のように見えますが、実際には、経済の戦場──物価・エネルギー価格・株価・為替を通じて、私たちの生活に直結しています。ロシア・ウクライナ戦争をきっかけとした原油高や食料価格高騰は、その典型例で、現在も日本人の家計を苦しめています。
「戦争と経済の関係を理解すること」は、ニュースを正しく読み解く力であり、投資判断や生活設計に役立つ実践的な教養です。
加谷珪一さんの『「教養」として身につけておきたい 戦争と経済の本質』は、難解な経済理論や軍事戦略ではなく、戦争と経済の「本質」を誰にでも理解できるようまとめられている点で一読の価値があります。
- 戦争のコストと国力
- 国債・金利・インフレの仕組み
- 株価や景気への影響
- 地政学的な背景
- テクノロジーが変える戦争
- 戦争とビジネスのつながり
これらを体系的に理解することで、戦争を「自分ごと」として捉え、現代社会を読み解く力が得られるはずです。