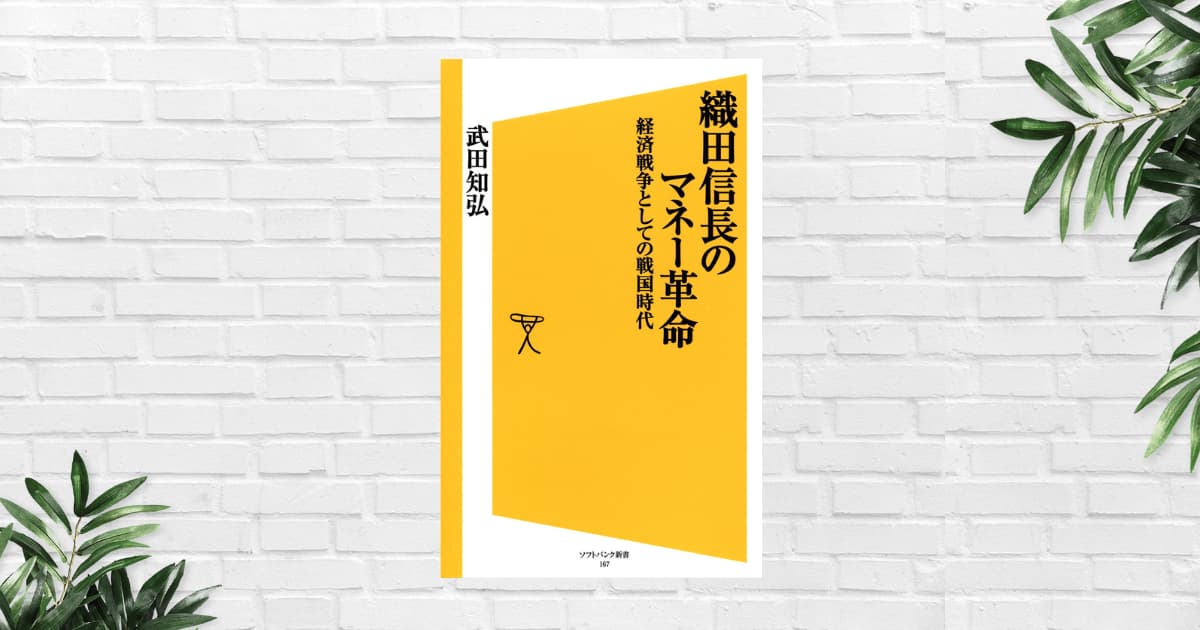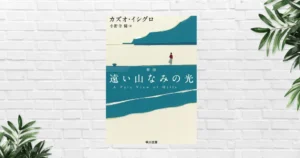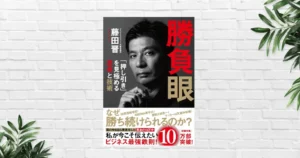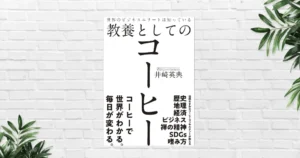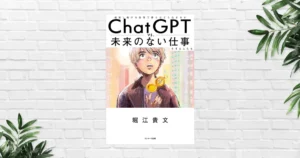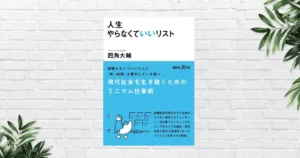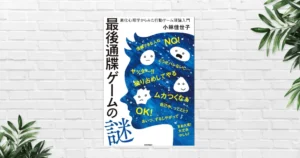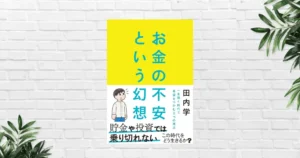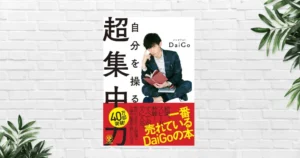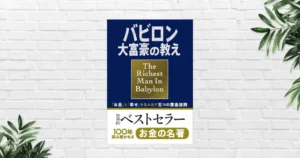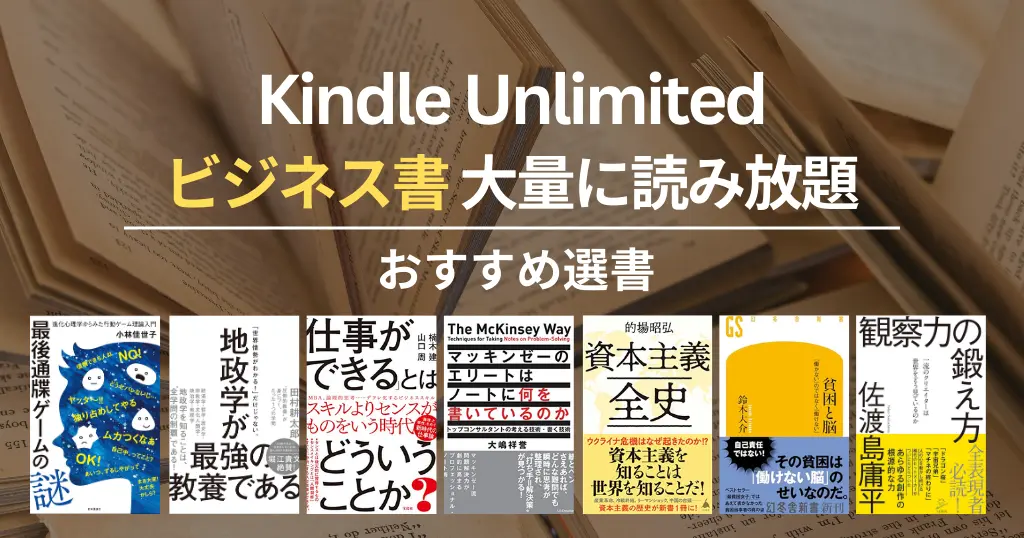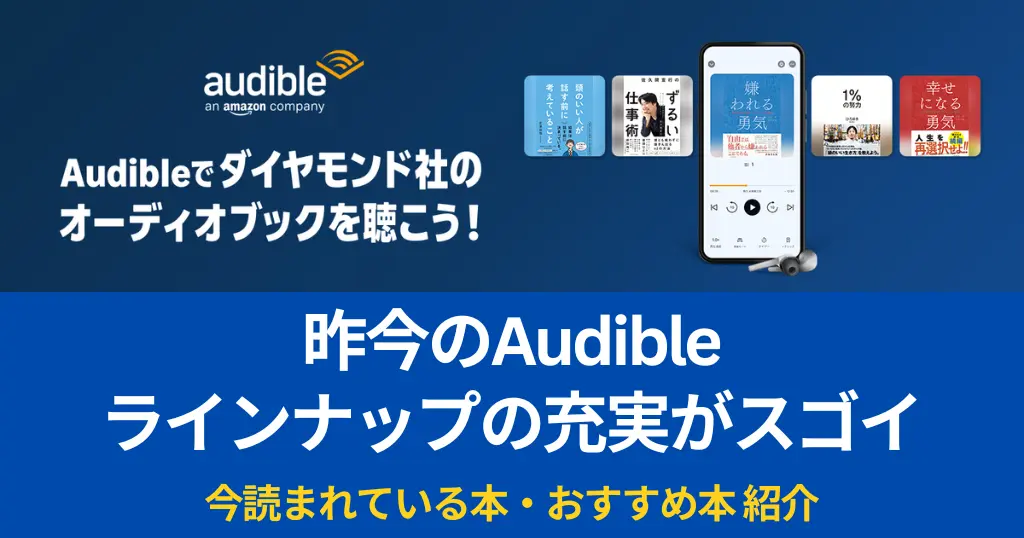- 信長の強さは「経済力」にあった
信長の強さは武力じゃない。港・寺・城を軸に経済を制した、富を生み出す仕組みを築いた“戦国の改革者”だった。 - 日本の経済制度の原型をつくった男
楽市楽座、関所撤廃、枡の統一など、信長の経済政策・都市政策は現代にも通じる。彼の改革が、現代につながる経済基盤を形づくった。 - 「お金の流れ」で歴史を見ると、今まで見えなかったものが見えてくる
★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本
『織田信長のマネー革命』ってどんな本?
【Kindle Unlimited】 最初の30日間体験無料🔥 ※対象者限定で「あなただけの特別プラン」も
「武力で天下を取った男」——そんなイメージが強い織田信長。
でも実は、彼の本当の強さは“経済力”と”経済戦略”にありました。
武田知弘さんの『織田信長のマネー革命』は、信長の非凡な経済センスとマネー戦略に光を当てた一冊。
歴史を「お金の流れ」から読み解くことで、これまで見えなかった信長の姿が浮かび上がります。
2025年9月、NHKスペシャルでは『戦国サムライの城 』が始まりましたが、第1目は「信長 驚異の“城郭革命”」。
本書を読むと、信長の築いた城が、日本の都市構造と税制度の原型をつくった“経済都市”だったことがより深く理解できます。
この視点で信長を見直すと、彼の先見性と実行力に、改めて驚かされること間違いなしです!
信長の強さの源は「経済力」

信長は、その類まれな軍事的センスで天下統一を果たそうとしたことで知られていますが、兵力・武器・武器製造技術整えるには「経済力」が必要です。
マネー改革の3つの柱― 港・寺・城
信長は、兵力や武器を揃えるために、領土よりも「港」を欲しがり、
特権階級だった「寺」を解体し、巨大な「城」を築いて都市を作りました。
この3つのキーワード——港・寺・城——が、信長の“マネー革命”の柱です。
- ⚓港(堺)を領地より重視。港を押さえることで、貿易と金の流通を支配
- 🛕寺(延暦寺・本願寺)など、経済を牛耳る特権階級を解体。宗教と経済の分離を断行
- 🏯城(安土城)をはじめとする都市型の城を築き、減税で人を呼び、儲けた者から税を徴収
信長は、ただの戦国武将ではなく、経済構造そのものを変えた“改革者”だったのです。
信長が築いた「日本の経済システム」
信長の経済における功績は「楽市楽座」だけではありません。信長の政策は、現代にも通じるほど革新的でした:
- 「金銀」を通貨として流通させ、貨幣経済の基礎を整備 → 日本の通貨整備の基盤づくり
- 商取引の単位「枡」を統一し、税の不正を防止
- 「関所」を撤廃し、物流を促進
- 「楽市楽座」で市場を開放し、減税で庶民も呼び込み、物価を下げて商業を活性化
これらの改革は、江戸時代の経済制度の原型となり、現代の日本経済にもつながる仕組みとなりました。
中でも、❶「お金=貨幣」は経済の根幹。
戦国時代の日本では、通貨制度が混乱していました。中世までは中国から輸入した銅銭が主流でしたが、明が禁輸を始めたことで、日本国内で貨幣が鋳造されるようになったものの、統一された価値基準がなく、流通は不安定でした。そこで、織田信長は「安定した貨幣経済」を目指し、金・銀を通貨として流通させる大胆な政策を打ち出したのです。
信長は、貨幣が社会に浸透するために必要な2つの条件を見抜き、それを見事に実現しました。
1️⃣ 通貨の十分な供給:
貿易港「⚓堺」を支配し、海外から金を輸入。「名物狩り(贈答)」で金を集め、積極的に市中へ放出
2️⃣ 通貨への信頼と価値の裏付け:
信長自身が集めた金を実際に使用し、「金銀は使える通貨だ」と世間に示す→貨幣としての信任を高め、流通を促進
📌戦国時代の金:武田信玄の「甲州金」
こちらは、通貨の流通条件を満たすには至らず → 信玄は武力だけでなく、マネー戦略も信長にには叶わず
【深堀り】マネー改革の3つの柱― 港・寺・城

【港】堺を押さえた信長の経済戦略
戦国時代、堺は日本でも屈指の国際港でした。
海上交通の要所であり、貿易によって莫大な富が集まる場所。
武器や火薬の材料となる硝石なども堺を通じて取引されており、軍事力を支える経済の中心地でもありました。
織田信長は、この堺の重要性を早くから見抜いており、どうしても手に入れたいと考えていました。
そこで、1568年、信長は将軍・足利義昭を奉じて上洛し、畿内を制圧。
その褒美として、堺・大津・草津に代官を置く許可を得ます。
- 堺:貿易と武器の流通拠点
- 草津:京都から琵琶湖への玄関口
- 大津:京都から北陸へ抜ける通過点
これらは、経済・交通・軍事のすべてにおいて極めて重要な拠点。
他の戦国武将から見ても、信長が手にしたのは“勝利への道”そのものでした。
1575年、信長・徳川連合軍と武田勝頼軍が激突した「長篠の戦い」。
武田軍は騎馬隊で圧倒的な強さを誇っていましたが、信長は火縄銃による「三段撃ち」でこれを打ち破ります。
この勝利の背景には、堺を押さえたことで鉄砲や火薬を安定して調達できた信長の経済力があったのです。
🛕【寺】信長が挑んだ“巨大特権階級”の解体
織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちし、石山本願寺と戦ったのは、単なる宗教弾圧ではありません。
その本質は、「経済と政治を牛耳る巨大特権階級=寺社勢力」を解体するための革命的な行動でした。
平安時代末期、白河上皇が「思い通りにならないもの」として挙げたのが、比叡山の僧。
それほどまでに、寺社は長きにわたり国家権力を超える存在でした。
- 延暦寺は全国に荘園を持ち、莫大な富を蓄積
- 寄進された資金で高利貸しを行い、返済できない者には「罰が当たる」と脅して取り立て
- 絹・酒・麴・油など、生活に欠かせない物資の流通も独占
まさに、宗教の皮をかぶった“経済財閥”だったのです。
一方、石山本願寺は、楽市楽座の発祥地。寺内町には商人が集まり、寄進によって巨大な経済力を持っていました。
- 堺の商人と連携し、渡明船を建造
- 全国から商品を集め、輸出入を行う“戦国版の総合商社”を目指していた
さらに、寺院は石垣や山城を築く技術、鉄砲を製造する技術まで持ち、軍事力すら備えていました。
根来寺は鉄砲三大産地の一つ。信長が脅威を感じたのも当然です。
故に、信長は、寺社のあまりに強大すぎる権力を「天下統一の障害」と見なし、徹底的に排除しました。
その結果、日本では宗教が政治や経済に過度に介入することがなくなり、現代に至るまで宗教の影響が比較的少ない社会が築かれたのです。世界的に見ても、日本ほど宗教の影響が小さい国はありません。
🏯【城】信長がつくった「城下町」の原型──安土城の都市革命
現在、日本の多くの県庁所在地は「城下町」を起源としています。
その原型となったのが、織田信長が築いた「安土城」でした。
信長は、交通と商業の要所に軍事機能を備えた都市を計画。その拠点に選ばれたのが、琵琶湖のほとりに位置する安土です。当時、琵琶湖は京都から関東・東北・北陸へ向かう交通の大動脈です。
信長はこの地に城を築き、京都への緊急対応も可能なインフラを整備。まさに、軍事・経済・交通が融合した“戦略都市”を作り上げたのです。
城の建設には莫大な費用がかかります。それでも信長は、安土城をはじめ、何度も大規模な築城を行いました。
しかも、庶民に重税を課すことなく――
その秘密が、上述した減税で人を呼び、儲けた者から税を取る「信長のマネー改革」(税制改革)💰にありました。
この仕組みにより、民衆の不満は少なく、一揆や反乱も起きにくい安定した統治が実現したのです。
最後に
武田知弘さんの『織田信長のマネー革命』は歴史の見方を変える一冊。
「武力の英雄」から「経済の革命家」へ——信長の真の姿を知れば、あなたの歴史観もきっと変わります。
信長の政治と経済戦略は、まさに現代の経営者のような発想であったことに驚かされました。
- 現状の問題点を直視する
- 前例にとらわれず、合理的な解決策を探る
- 粘り強く実行し、成果を出す
なお、日本の県庁所在地の都市のほとんどは、「城下町」が発展したものです。この「城下町」の原形が「安土」にあったとは。現在の日本の礎を築いた偉人の凄さを改めて思い知らされました。
お金から物事を見ると、本当に、歴史・世の中がよく見えます。是非、皆さんも本書を手に取って、多くの学びを手にしてください。
映画化&コミック化された『もしも徳川家康が総理大臣になったら』では、織田信長は経済産業大臣として登場!
本書を読んだ方なら、なぜその配役なのか、きっと納得できるはずです。まだ読んだことがない方は、是非、合わせ読みを!