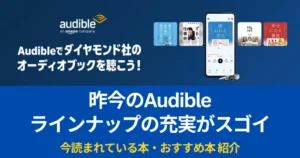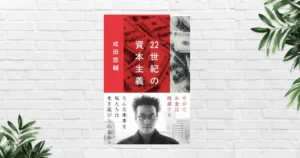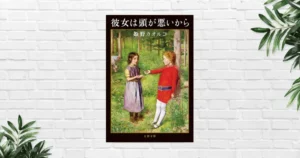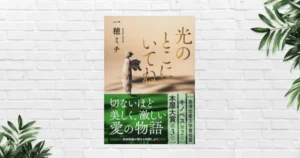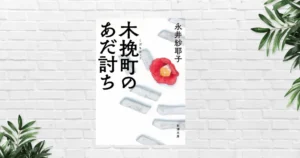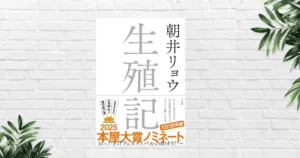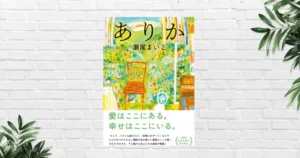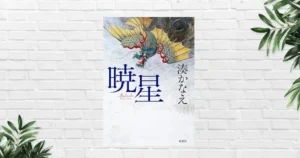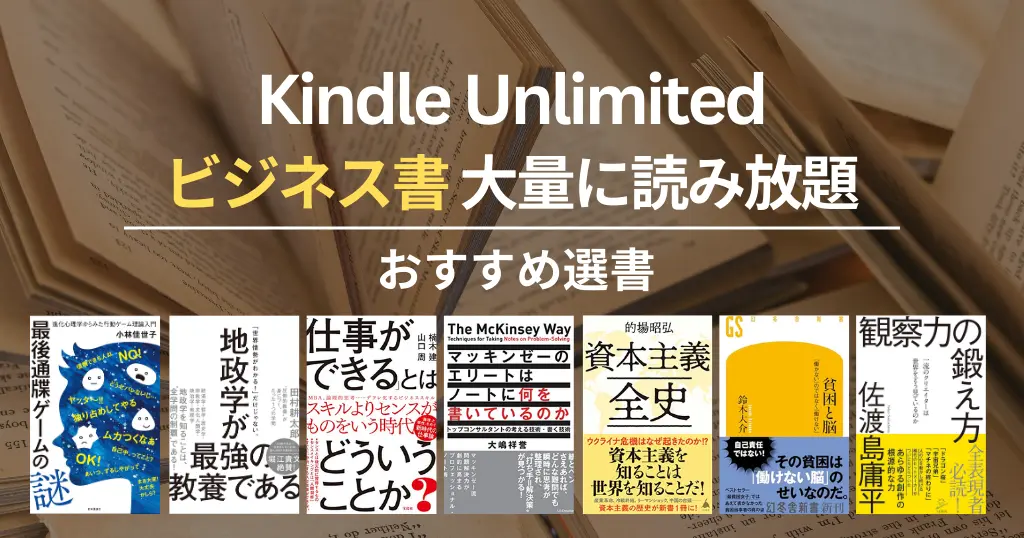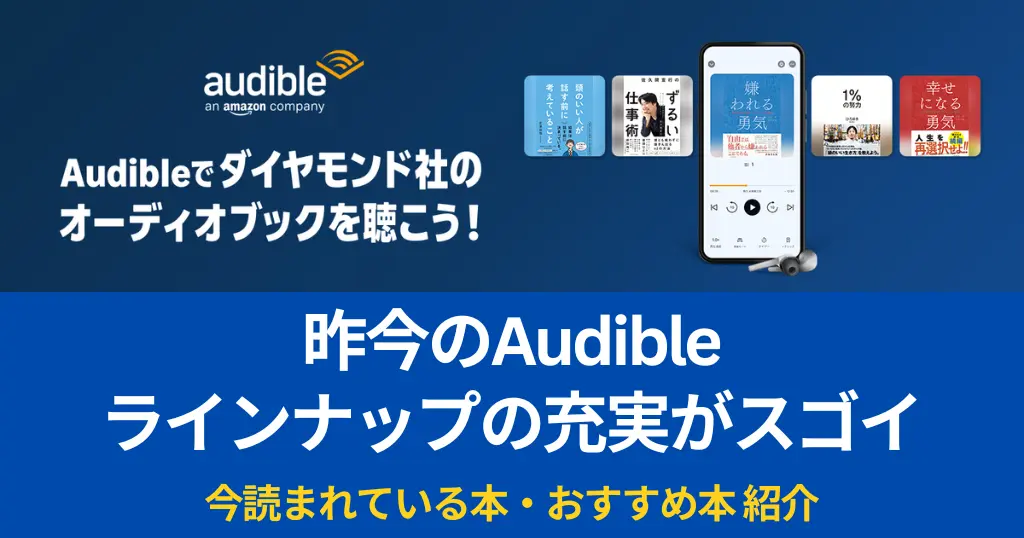- 科学✕人間ドラマ。直木賞受賞作
地質学、生物学、天文学といった様々な分野の専門知識が物語の根幹を支える5つの人間ドラマ。ちっぽけな一人の人の人生と、数万年という地球の歴史、そして、人に紡がれた伝統が深くつながる。 - 静けさの中に息づく時間の重み
『宙わたる教室』とは異なる、淡々とした筆致。しかし、その「静けさ」に本作の良さがある。 - 本書を読むなら
読書中は、作中に散りばめられた科学的な事実に手を止め、関連情報を調べてみたい。読了後は、私たち自身の存在や、この世界との繋がりについて、じっくりと考えたい。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『藍を継ぐ海』ってどんな本?

作家・伊与原新さんの名は知らなくても、NHKでドラマ化された『宙わたる教室』はご存じ、という方は多いでしょう。
伊与原作品の最大の魅力は、科学 ✕ 人間ドラマ。
東京大学大学院で地球惑星科学の博士課程を修了したという異色の経歴が「武器」となり、その科学的な知見が、物語の骨格を成し、そこに温かい人間ドラマが息づいています。
第172回直木賞を受賞した短編集『藍を継ぐ海』もまた、地質学、生物学、天文学といった様々な分野の専門知識が物語の根幹を支える作品です。単なるエンターテインメントにとどまらず、5つの人間ドラマを通じて知的好奇心を刺激し、少しだけ世界の見方を変え、私たち自身の存在や未来について深く考えるきっかけを与えてくれます。
『藍を継ぐ海』は、感情を直接揺さぶるような物語ではありません。静かな作品です。最初、淡々とした執筆に物足りなさを感じるかもしれません。しかし、その「静けさ」に本作の深さ・味わい深さがあります。
あらすじ:科学、歴史、そして人間ドラマが重なる5つの物語
本書に収められた5つの物語は、日本各地の知られざる土地を舞台に、私たちの足元の「地球」と、その上で紡がれてきた「人間の営み」の奥深さを描き出しています。
- 「夢化けの島」
山口県の火山島「見島」が舞台。地質学者が、萩焼に使われていたという伝説の土を探す怪しげな男と出会う。
長い年月をかけて形成された地質と、人の歴史が交錯する、ラストに心温まる物語。 - 「狼犬ダイアリー」
東京での挫折から奈良の山奥へ逃れた女性が、絶滅したはずのニホンオオカミらしき動物を目撃。
ニホンオオカミの歴史、そして、失意の人生に光を灯す、野生との出会いが描かれる。 - 「祈りの破片」
長崎の長与町が舞台。空き家から放たれる青白い光の謎を追う役場職員が、ある男の壮絶な人生と、歴史の悲劇に隠された科学者の「使命」に触れる。被爆地・長崎の“伝えるべき記憶”に深く切り込んだ一作。 - 「星隕つ駅逓」
北海道の過疎の町で、隕石を発見した妊婦が、ある理由からその発見場所を偽ろうと画策する。
そこにあるのは、宇宙のロマンと過疎の町を守ろうとする思い。地域の歴史が親子の絆と交錯する物語。 - 「藍を継ぐ海」(表題作):後述
それぞれの物語は完全に独立しています。しかし、5編の物語にはそれぞれ、土地に根ざした地球の「科学」と「歴史」が静かに息づいています。そして、そこに人々の歴史=「人生」、そして、人生につきものの「悩み」や「葛藤」など、人間ドラマが重なります。
読み進めるごとに、読者は、ちっぽけな一人の人の人生と、数万年という地球の歴史が深くつながっていることに気づかされるでしょう。
感想:「静けさ」の中に息づく時間の重み
私は本作を読み始める際、『宙わたる教室』のような、手に汗握る展開を期待してしまいました。そんな気持ちで読み始めると、淡々とした執筆に物足りなさを感じるかもしれません。しかし、次第に、その「静寂」にこそ、本書の深遠な意味があることに気づかされます。
『宙わたる教室』が、定時制高校の科学部という限られた空間での生徒たちの葛藤と成長を描く「凝縮された時間の物語」であるならば、『藍を継ぐ海』は、「地球・伝統」といった時間の中を生きる人を、静かに描く物語です。
「淡々」とした描写の裏には、地球の悠久の歴史、そして何世代にもわたって受け継がれてきた伝統の重みが、静かに息づいています。忙しく毎日を過ごしている私たちがつい見過ごしがちな、地球の営みや生命の軌跡、受け継がれていく伝統、そして環境問題の根深さを、自分の心でじっくりと感じ取ることができるはずです。
【考察】なぜ、『藍を継ぐ海』が表題作なのか?

複数の短編から成る作品集を読むたびに、なぜその作品が表題作として選ばれたのか、と考えるのは読書の楽しみの一つです。
私の勝手な考察ですが、本作が「時間スケール」だけでなく、「空間スケール」も壮大な作品である点が大きいと感じます。このスケールこそが、短編集全体の「顔」となるにふさわしいのでしょう。
『藍を継ぐ海』は、徳島の海岸で少女・沙月がウミガメの卵を盗むところから始まります。この物語のベースとなる科学は、ウミガメの「母浜回帰(ぼひんかいき)」という生態。地図も持たないウミガメが、何十年も太平洋を回遊し、生まれ故郷の浜に帰ってくる。この驚異的な事実に、少女の複雑な家庭環境と、未来への不安が絡めて描かれます。
「なぜ、母親も姉も私を置いていったのだろう」——孤独を抱える沙月が、見捨てられる恐怖を乗り越え、自らの手で命を孵化させ、広い海へ放つことで、自分自身を解放しようとするのです。
もう一つ、物語で大事な要素が「藍」。徳島の伝統「阿波藍」、黒潮の深遠な藍色、さらに遠い祖先から受け継がれる遺伝子に刻まれた「記憶の流れ」までもが、この「藍」という言葉に凝縮されています。
私たち人間もまた、ウミガメのように、ふと生まれ故郷に帰りたくなります。人もまた、「故郷回帰」する存在。それは遺伝子に刻み込まれているのかもしれません。自身のルーツ・受け継がれていく命、そして故郷について、静かに問いかけられる作品でした。
最後に──本書を読み終えて
今回は、直木賞受賞作品、伊与原新さんの『藍を継ぐ海』を紹介しました。
私たちの人生は、地球を前にすると、取るに足らない存在に感じられます。
しかし、私たち人類も、遠い過去から命を受け継ぎ、未来へと手渡していく「命を継ぐもの」です。命をつないでいくため、自分・社会・子孫が幸せになるように努めて生きることこそが、私たちに課された使命なのかもしれません。このようなことは、本作の中を流れるゆったりとした時間軸で考えるからこそ、感じ取れるこそです。
一方で、物語では、日常に行き詰まりを感じ悩んだり、あるいは困難から逃げ出してしまったりした人々が、科学や歴史、そして自然との出会いを通じて、もう一歩先へ足を踏み出そうとする姿が描かれます。これも、静かな感動と勇気を与えてくれるはずです。
ぜひ、辺境の地に旅に出るつもりでこの本を手に取ってみてください。旅のように、あなたも何か大切なものに出会えるはずですから。
どちらもAudible聴き放題で読めます。