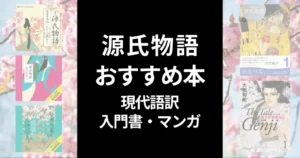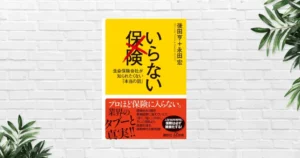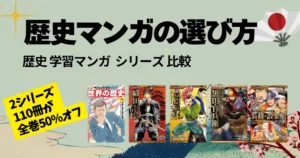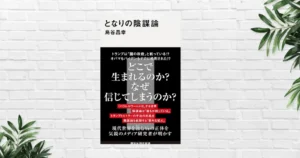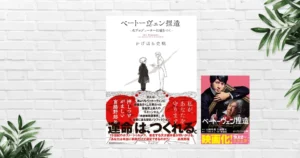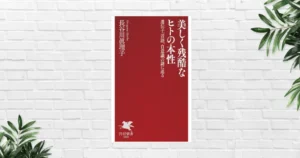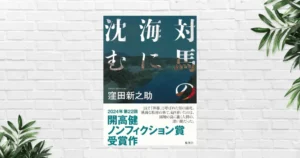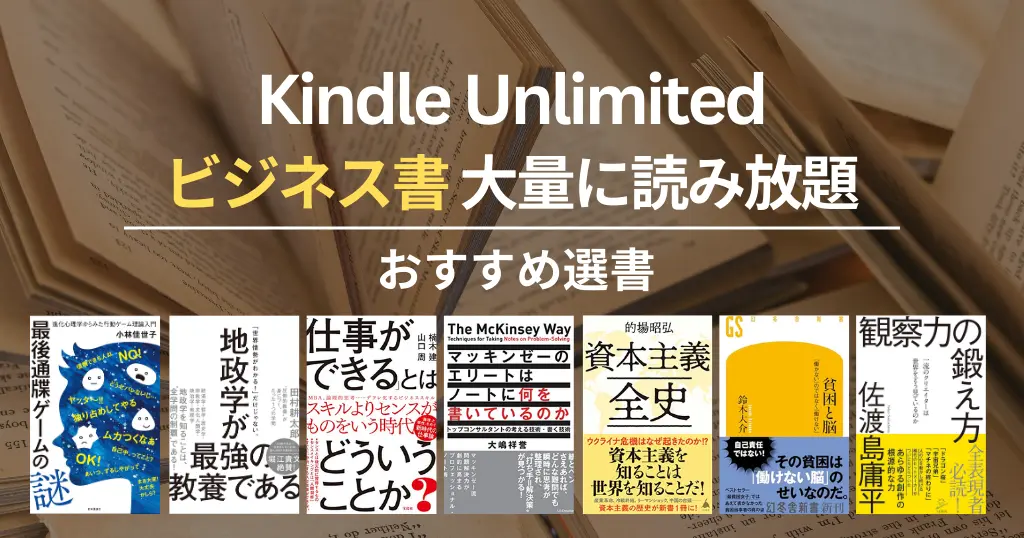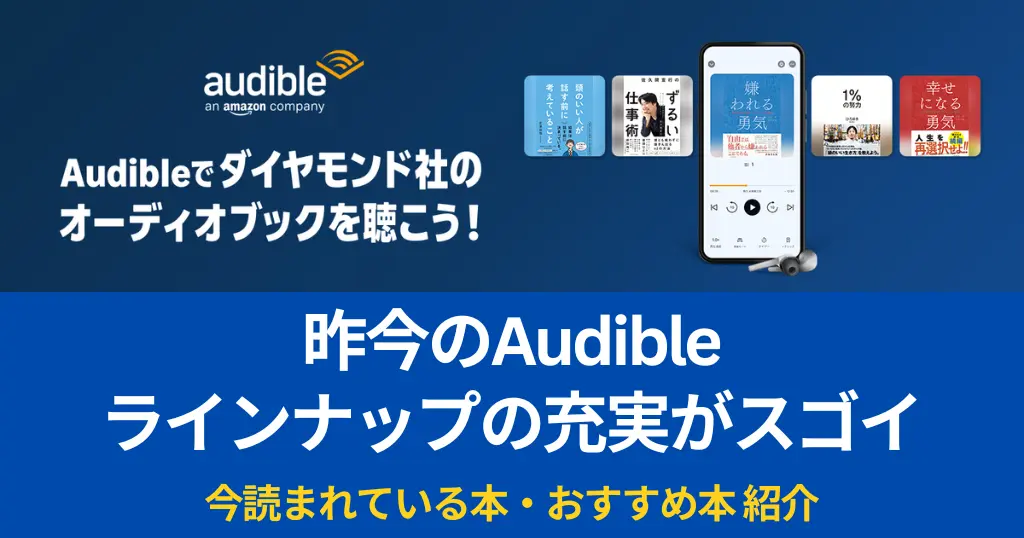- 「らせん訳」で、物語は“進化”する
『源氏物語』は、原典→ウェイリー英訳→現代日本語という往復運動の中で、言語と文化が重なり合い、らせん状に新しい姿へ進化する。“戻す翻訳”ではなく、時代と文化をまたぐ再創造として再生される。 - ウェイリー版 源氏物語
20世紀初頭のイギリス文化、宗教観、時代の空気は、ウェイリーの英訳に色濃く入り込み、紫式部の世界と融合。姉妹はその“異物感”を排除せず再構築し、第3の源氏物語が立ち上がる過程を丁寧に描く。 - 翻訳とは「作品をもう一度つくる」創造行為だった
本書の最大の気づきは、翻訳とは単なる言語の置き換えではなく、文化・時代の雰囲気までを含んで書き換えられる“トランスクリエーション”。その理解は、これから読むすべての翻訳書への視点を深く変える。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『レディ・ムラサキのティーパーティ』ってどんな本?
2025年11月、NHK「100分de名著」で再び取り上げられたのが、アーサー・ウェイリー版『源氏物語』。
再放送とはいえ、その魅力が丁寧に掘り下げられ、“古典が世界文学へ生まれ変わる瞬間”を目の当たりにする内容でした。
番組をきっかけに手に取ったのが、毬矢まりえさんと森山恵さん姉妹による
『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』。
千年前に紫式部が書き、百年前にウェイリーが英訳し、そして現代日本語に“再翻訳”される——。
この奇跡の三重奏から生まれた「物語の進化」を解きほぐすのが本書。
知的でありながらチャーミング。
姉妹は、ウェイリー英訳から現代語への“らせん訳”を担った当事者でもあります。
多くの人にとって『源氏物語』は、
- 「授業で眠くなった…」
- 「昔のプレイボーイの話でしょ?」「難解な恋バナのどこが面白い?」
そんな固定観念の象徴でもあります。しかし本書は、そのイメージをくるりとひっくり返してしまいます。
これは、古典解説でも翻訳論の教科書でもありません。
千年と百年、日本とヨーロッパ——時空をひとまたぎに横断する“文学と翻訳の冒険譚”のようです。
姉妹・ウェイリー・紫式部が語り合う「ティーパーティ」
「えっ、ここで、この表現!?」
「ねえ、ウェイリーさん。この単語を選んだのには、こんな意図があったのでは?」
「紫式部さん、きっとあなたは、ここでこんな気持ちを表現したかったのよね。」
「さて、この素晴らしさを多くの人に知ってほしい! どう“らせん訳”したらいいかしら?」
本書は、上記のような 訳者姉妹と、紫式部、ウェーリーとの会話が聞こえてきそうな本です。
軽やかな文学解説・翻訳秘話が、文学の重厚さをふわりとほどいていきます。
ページをめくるたび、姉妹・ウェイリー・紫式部の4人の、時代を越えたティーパーティー談議の光景が自然と浮き上がってくるようです。
文学の難しい話も、姉妹の柔らかい語り口によって、友人同士のおしゃべりのようにスッと入ってきます。
キーワードは「らせん訳」――物語は“進化”する

本書の中心にあるのが「らせん訳」という概念。
原典(千年前/日本)→ ウェイリー英訳(百年前/イギリス)→ 現代日本語(いま/日本)
この往復運動が らせんを描き、物語が“上へ進化する”という考え方です。
たとえば『源氏物語 ウェイリー版』の冒頭は次のように始まります。
いつの時代のことでしたか、あるエンペラーの宮廷での物語でございます。
ワードローブのレディー(更衣)、ベットチェンバーのレディ(女御)など、
後宮にはそれはそれは数多くの女性が従えておりました。
その中に1人、エンペラーのご寵愛を一身に集める女性がいました。
その人は侍女の中では低い身分でしたので、成り上がり女とさげすまれ、憎まれます。
あんな女に夢をつぶされるとは。わたしこそと大貴婦人(グレートレディ)たちの誰もが心を燃やしていたのです。
エンペラー、レディ、プリンス……。
古典語訳では決して見慣れない単語が並ぶのに、なぜか読めば読めるほど魅了される。
そして、英語圏の宮廷世界が広がってくる。
それは、まるで 異世界ファンタジー! 驚きの感動で、千年前の物語の世界が広がるのです。
この“異物感”を、姉妹は排除せず、素材として大胆に活かしていく。その結果――
原典でもない。
英訳でもない。
現代語訳でもない。
“第三の源氏物語”が生まれた。 というのです。
ウェイリー版には、
紫式部の宮中文化 × 20世紀初頭ヨーロッパの美意識
という文化の掛け合わせが確かに息づいています。
【参考】ウェーリーが生きた時代と。彼の「源氏物語」
ウェーリーは、20世紀初頭を生きた英国人。
彼が生きた時代は、イギリスが世界の覇権を握る「大英帝国」から没落していく時代。ヨーロッパの各国が覇権を争い、第一次世界大戦によって荒廃した時代です。そんな中、東洋のジャポニズムがイギリスの知識層を席巻していました。
そんな彼の世界観・宗教観・時代の空気—— は、避けようもなく彼の翻訳に染み込んでいます。
私の読書ライフに“地殻変動”——最大の気づき
本書を読み進める中で、私が最も強くハッとさせられたのが、
翻訳とは「トランスクリエーション(創造的翻訳)」であるという指摘でした。
それまで私は、翻訳を「原文を別の言語に置き換える作業」としか考えていませんでした。
しかし、翻訳者は言語を移すだけでなく、
文化・価値観・時代の空気・宗教観・物語のリズム など、
目に見えない層すべてを読み取り、別の文化圏の読者が “わかる” ように再構築している。
つまり翻訳とは——作品を別の時代・別の文化圏の中で“もう一度つくる”行為。
一冊の翻訳本の背後には、複数の文化が折り重なり、複数の時代が対話している。
翻訳書を読むということは、原作者と翻訳者、そしてその時代までも読むことなのだと。
言われてみれば、“当たり前のようで実は多くの人が気づいていない、翻訳の真実”
この気づきは、私の読書ライフにとって、小さくない“地殻変動”でした。
これから読むすべての翻訳作品の奥には、見えない声のレイヤーが積み重なっていることを意識して読みたいです。
まとめ―― 読後に残るもの
『レディ・ムラサキのティーパーティ』を読み終えて残ったのは、
翻訳とは言葉の置き換えではなく、文化と時代を渡る“再生の営み”だという大きな気づきでした。
千年の時を経てもなお『源氏物語』が読み継がれているのは、原典の魅力に惹かれた多くの訳者たちが、世代ごとに「らせん状の翻訳」を重ねてきた成果なのだと感じます。
思えば、名著を集めたシリーズでも、「岩波文庫」よりも新しい訳を収めた「光文社古典新訳文庫」の方が読みやすいことが多いのです。これは、現代に即した表現や感覚が取り入れられているからこそ、読者にとって親しみやすくなっているのだと思います。
本書は、源氏物語の再発見を超えて、翻訳とは何か、読書とは何か
その根本を問い直してくれる一冊となりました。読書をより深く味わいたい方に、是非、おすすめしたいです。
いつでも解約可能