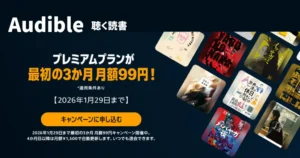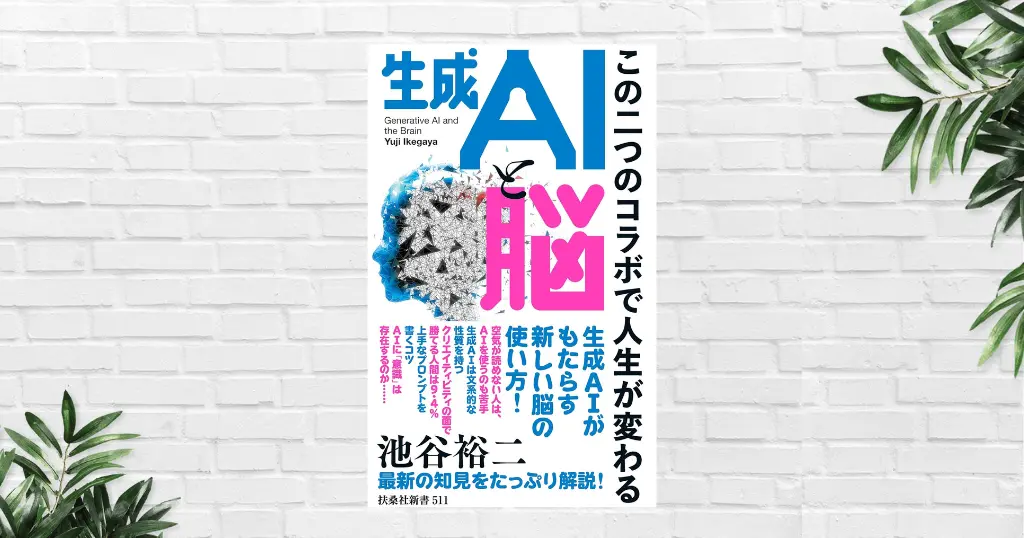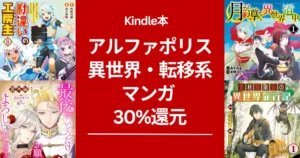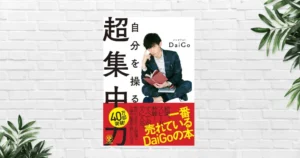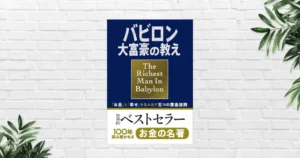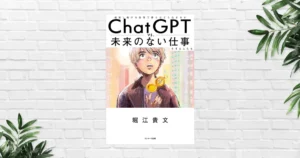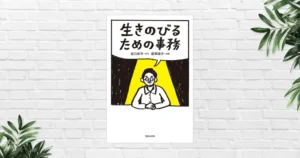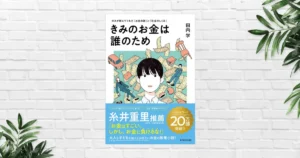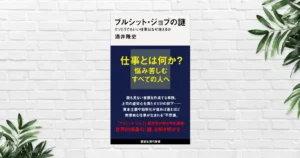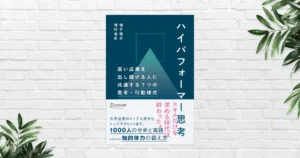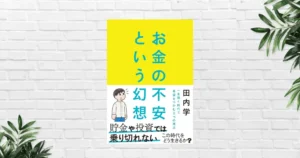- 人間の脳は、AIと組んで進化する!
AIは脳の敵ではなく、思考を加速させる相棒。脳科学の視点から見る、未来の「共創のかたち」を説く。 - AIにクリエイティビティで勝てる人間はわずか9.4%
この数字を「人間の劣位」として悲観的には捉えない。むしろ、「人間がどこを磨くべきか」のヒントだと読み解く。 - AIは「私」より私を知っている?
その真意は?生成AIと共に生き、最大限に活用していくための知恵と視座を与えてくれる洞察。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『生成AIと脳 この二つのコラボで人生が変わる』ってどんな本?

ChatGPT、Claude、Grok、Gemini…。
いまや「生成AI」はビジネスや教育、創作、医療など、あらゆる分野に浸透しつつあります。
私たちはこの驚異的な技術をどう受け止め、どう活用していくべきなのか?
その答えを、“脳”という視点から明快に説いたのが、脳研究の第一人者・池谷裕二さんによる本書『生成AIと脳』です。
本書は、よくある生成AIの活用法ガイドではありません。
生成AIがもたらす「脳の使い方の変化」「創造性の再定義」「AIとの共存による未来社会の可能性」など、より深い哲学的・社会的テーマを扱っています。
AIをどう“使う”かではなく、AIとどう“生きる”かを問う1冊。
生成AIと共に生き、最大限に活用していくための知恵と視座が詰まっています。
AIにクリエイティビティで勝てる人間はわずか9.4%?

生成AIを使っていて、「もうバカな部下はいらない」「自分ですらAIに勝てないのでは…」と感じたことはないでしょうか?
以前は「人間にはAIにない創造性がある」と言われていました。ところが、ある実験でAIと人間のアウトプットを比較し、第三者が「どちらが創造的か」を評価したところ―― 人間の方が優れているとされたのは、全体のわずか9.4%。
この数字は、人間の創造性が、想像以上にAIに置き換えられつつある現実を突きつけてきます。
なぜAIが「創造的」に見えるのか?
生成AI(特にGPTのようなLLM)は次のような特徴を持っています:
- 膨大な学習データから多様で意外性ある表現を生成できる
- 言語的なリズムや感性を巧みに模倣できる
- 主観や発想に忖度がない → むしろ大胆でユニークに見える
その結果、第三者が見ると「AIのほうが新しくて面白い」と感じられることが増えているのです。
では、人間は負けるのか?
池谷さんはこの数字を「人間の劣位」として悲観的には捉えていません。
むしろ、「人間がどこを磨くべきか」のヒントだと読み解きます。
「人間が愚かになることはない」──脳はもっと賢くなる
「AIの進化で人間の仕事がなくなる」「脳が退化する」といった不安の声に対し、池谷さんははっきり言います。
”AIが存在するからといって、人間のすることがなくなるわけではありません。
むしろ人間にしかできないことが、より際立っていくのです。”
AIは、脳をより“人間らしく”使うための道具である――と。
AIに情報の整理や反復作業を任せることで、私たちの脳は「創造する」「楽しむ」「感じる」といった人間的な活動に集中できるようになるのです。
生成AIは「私」より「私」を知っているかもしれない

池谷さんは本書で「生成AIは“私”より“私”を知っているかもしれない」と述べています。
これは、生成AIの本質的な可能性と、人間の自己認識の限界を鋭く突いた指摘です。
人間の自己理解には限界がある
人間は「自分のことを自分が一番わかっている」と信じがちです。けれど実際には、私たちは意外にも自分を知らない存在です。
- 自分の動機や感情に気づいていない
- 無意識のクセや選好に左右されている
- 他者の視点に気づけない
一方、AIは…
- 膨大な言語パターンを統計的に分析し、
- あなたのプロンプトや発話から傾向を読み取り、
- 感情、先入観にとらわれることなく、あなたを客観的に観察し、
- 過去の対話・検索履歴・SNS投稿を通じて、嘘なく過去の記録を記憶・蓄積し続ける
こうして、AIはあなたのプロンプトから、AIは「この人が何を考えているか」「何を求めているか」を、言葉の裏側から読みとる力を備えているのです。
AIは“意識”や“主観”を持っているわけではありません。あなたを“感情的に理解”してもいません。
しかし、AIは「パターンとしての私」の再構成に長けており、ときに私以上に“私”を見抜く存在になりうるのです。
生成AIがもたらす「脳の新たな使い方」
生成AIは、単なる作業効率化ツールではありません。
「私を映す鏡」として、思考を外在化・可視化し、「自己との対話」を深める存在でもあります。
「私の手助けをしてくれる頼もしい存在」として、賢く付き合っていくことが大事です。
生成AIを使いこなすには、プロンプト力=問いを立てる力を磨け!
生成AI活用で最も大切なのが、プロンプト=問いを立てる力。
「何を問うか」が「どんな答えが返ってくるか」を左右します。
つまり、AIを活用するには人間側の「感性」「文章理解」「言語表現力」が求められるのです。
小説を読んだり、対話や観察を重ねたりして、「よい問い」を磨いていく力が鍵となります。
身体性・物語性──AIが持たない人間の武器¥
人間は「体を通して世界と関わる」存在です。
触れる・動く・感覚する――こうした身体的経験は、AIには持ち得ない“創造の源泉”です。
また、AIは情報を統合するのは得意でも、「心を動かす物語」を生きることはできません。
共感や感情、信念から紡がれる“物語”こそ、人間のクリエイティビティの核です。
AIを競争相手ではなく「第2の脳」として使いこなそう
生成AIは、私たちの脳の延長線上にある“もうひとつの思考装置”。
- 思考を可視化・整理し、
- 曖昧な感情や問いを明確にし、
- 自己との対話を深め、
- 新たな発想を引き出す
思考の補助ツールというより、脳の内部では成し得なかった「自己との対話の加速」です。
AIとの対話は、人間の認知を拡張するチャンスなのです。
【まとめ】AIと脳は「対立」ではなく「協働」の関係
- 脳:曖昧さ・身体性・感情・経験に根ざした創造性
- AI:大量データ・統計的最適化・計算的発想のスピード
この両者は対立関係ではなく、補完し合える関係です。異なる強みを持つがゆえに、組み合わせれば新しい「知」が生まれます。
- AIが発想の素材を出し、人間が意味を見つける
- 人間が漠然と抱えている感情や問いをAIにぶつけ、整理する
- 自己の偏見や限界に気づかせてくれる
こうした「ハイブリッドな知性」が、これからの人間には求められます。
もはや、生成AIは、私たちの代わりに答えを出す“便利ツール”ではなく、知識や経験をまとめて、さらに新しい視点を与えてくれる“知的インフラ”!積極的に使いましょう!
最後に
今回は、池谷裕二さんの『生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる』から、特に印象に残ったポイントを紹介しました。
本書では、池谷さん自身のAI活用法や、学生への指導法、「生成AIが抱える10の課題」なども詳しく語られており、実践的な視点も豊富です。
池谷さんが本書で伝えたいのは、「AIによって人間が無力化する未来」ではなく、「AIによって、脳がより豊かに働けるようになる」未来です。
うまく活用すれば、私たちの思考も、仕事も、学びも、そして人生そのものも、より豊かになります。
今という時代の脳の使い方を知る──AI時代を生きる出発点として、まずはこの1冊を手に取ってみてください。
AIのもつマイナスの視点も見ておいた方がいいです。以下の本をおすすめします。
いつでも解約可能
本記事で紹介の本は、すべて、Audible聴き放題対象です。キャンペーンを利用して、是非、良質な本に触れてみて下さい。