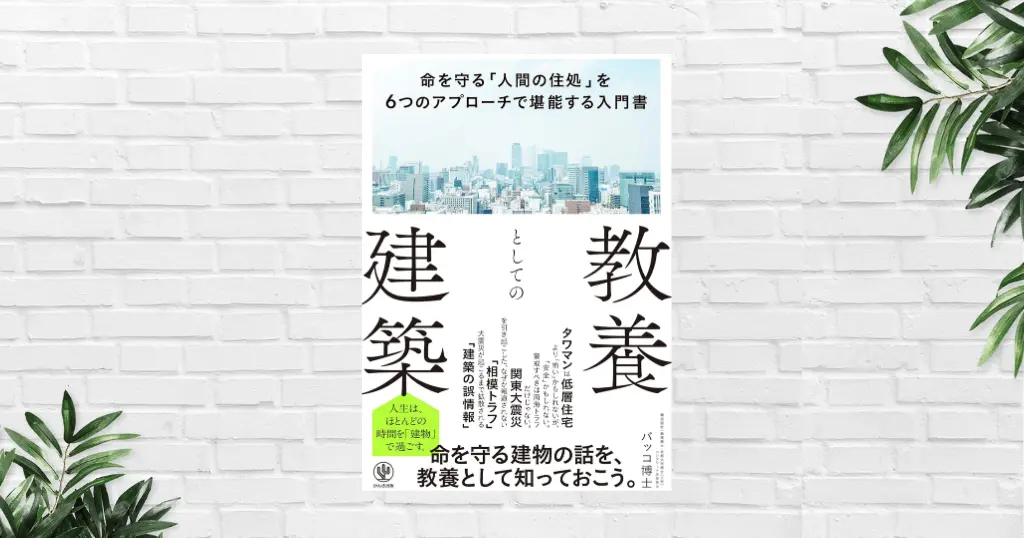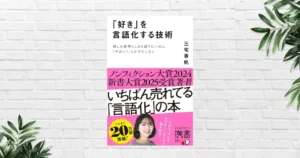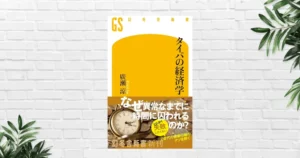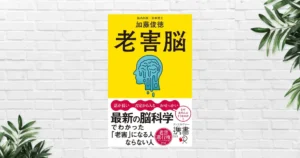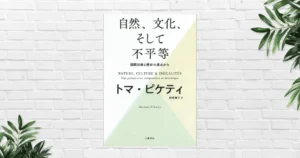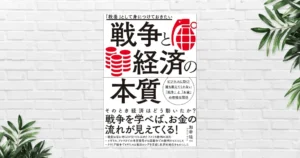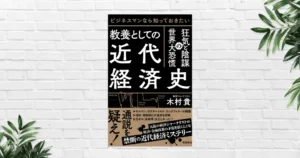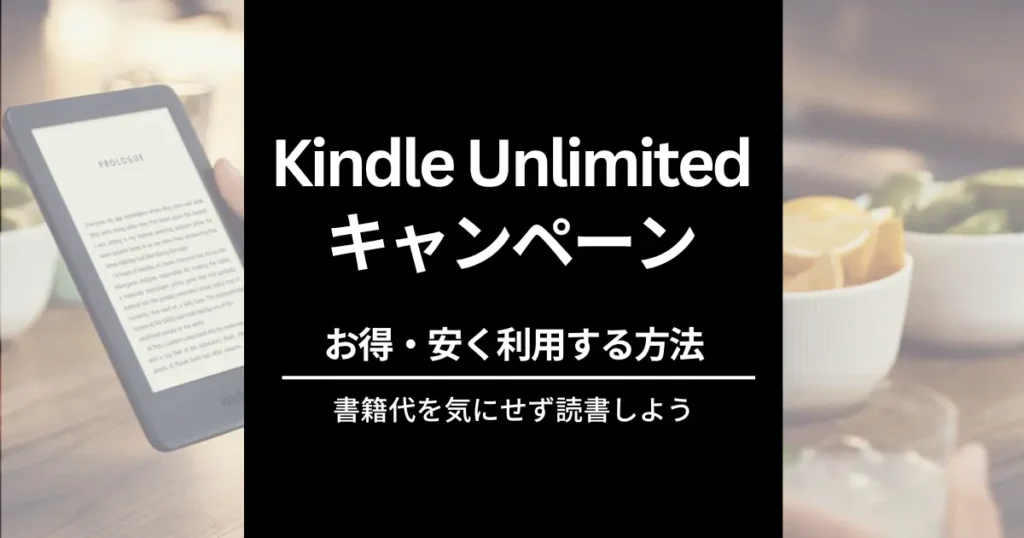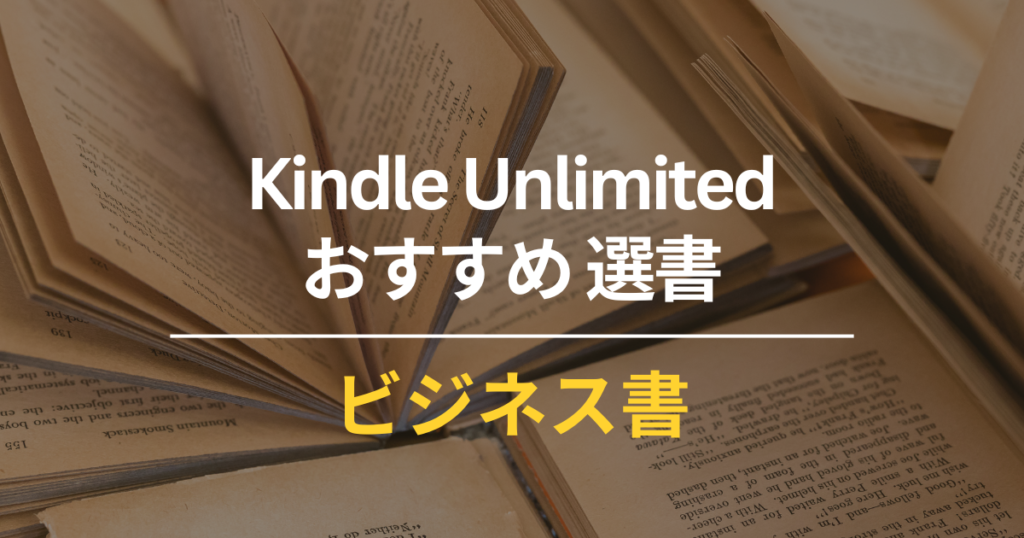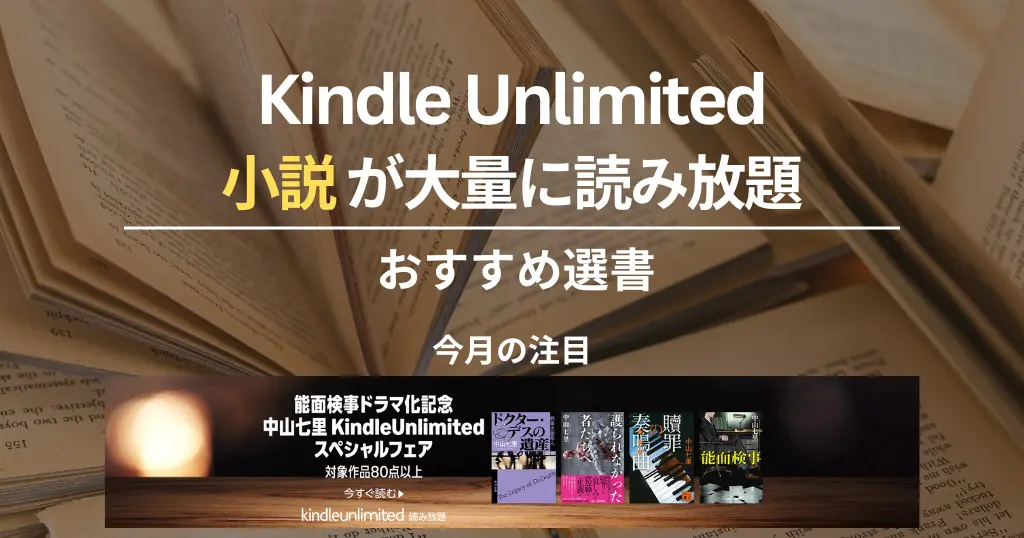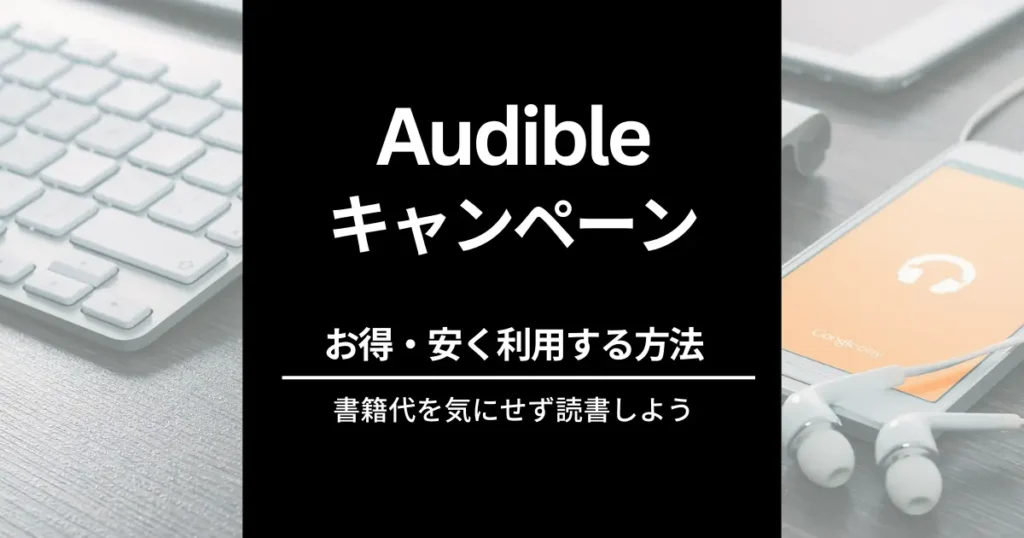- 建築は「不完全」が前提
完璧な建物は存在せず、誤差や劣化は前提。だからこそ「壊れ方」や「逃げ道」まで含めて考えるのが建築の本質。 - 賃貸選びにも役立つ“構造の目”が養われる
「どの階が安全か?」「耐震補強が逆効果になることも?」など、物件選びの判断軸が養える。 - 専門外でも読みやすい“建築の教養書”
数式なし。専門用語は最小限。日常の例を通じて、建築の見方が変わる一冊。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『教養としての建築』ってどんな本?

Audible:30日間体験無料! ※いつでも解約可
マイホーム取得は人生の大イベントですが、賃貸で暮らす人やオフィスを借りる企業にとっても「安全で快適な空間を選ぶこと」は同じくらい重要です。
本書『教養としての建築』は、建築の三要素「強(安全性)・用(使いやすさ)・美(デザイン性)」のうち、特に「強」=構造的な安全性ににフォーカスしたユニークな教養書。
著者は構造設計一級建築士であり京都大学博士のバッコ氏。専門的な知見を、一般読者にもわかりやすく語ってくれます。
建築が専門外の人には、多くの気づきがある1冊です。数式なし、専門用語は最小限。日常の例を通じて、建築の見方を変えてくれます。本記事では、私が本書を読んで気づかされたことを、3点に絞って紹介します。
建築は「不完全」なものという指摘
「壊れない家が理想」と思いがちですが、著者は「建築は不完全で、誤差や想定外に満ちている」と断言。
完璧を求めるほど危険になり、むしろ“壊れることを前提に設計する”ことが安全につながると説きます。
私たちは「壊れない家」を理想とします。しかし、著者は「建築は不完全で、誤差や想定外に満ちている」と断言。
完全さを求めると逆に危険であり、むしろ、壊れることを前提に、建築物を捉え直すことが安全につながると説きます。
- 建築は完璧であるべき → モノは必ず壊れる。建築は不完全であることを前提にすべき
- 人間がつくる以上、誤差は避けられない:施工現場では数ミリのズレや順序変更が日常茶飯事
- 材料にはばらつきがある:コンクリート、鉄骨、木材などは、同じ規格でも性能に個体差
- 使用環境は常に変化する:地盤・気候・人の使い方は、設計時の想定から変わる
- 構造計算は「仮説の塊」:素材・加重・接合条件など、すべて理想化された前提の上
つまり、建物は「信頼して使う」のではなく、「疑いながら守って使う」もの。
定期点検・大規模修繕を大前提に、避難経路の確保も大事。そして、技術の限界を理解することも重要です。
これらの指摘は、賃貸で暮らす人にとっても、建物をどう信頼すべきかを考える視点を与えてくれます。
📌自動車と建物の安全性は別物
自動車は衝突試験を繰り返して、均質な素材で量産されるが、建物は一点もの。
設計図・土地環境は、すべて異なり、壊して試すこともできない。
賃貸選びにも役立つ構造知識
「タワーマンションの高層階と低層階、どちらが安全か?」
「耐震改修したら逆に壊れやすくなることも?」
こうした疑問に、不動産を買う人だけでなく、借りる人にとっても重要な知識です。本書はそれを、構造の裏側から答えてくれます。
地震の多い日本では、建物の倒壊やひび割れのメカニズムを知っておくことが重要。
建材の特性や最新技術も紹介されており、家賃や立地だけでなく「構造的安全性」を判断軸にできるようになります
📌 鉄とコンクリートが主流な理由
互いの弱点を補完し合う理想的な組み合わせ。コスト・強度・施工性のバランスが良い。
最新テクノロジーを含め、こうした雑学的な知識も、本書の楽しみの一つ。
建築士の専門性を見極める視点
「評判の建築士=強い家を作れる」とは限りません。
建築士には複数の資格があり、設計できる建物の規模や専門性が異なります。
- 一級建築士、二級建築士
- 構造設計一級建築士
- 設備設計一級建築士
また、建築士の設計業務は「意匠設計(デザイン)」「構造設計」「設備設計」にに分かれており、住宅設計だけでは構造の専門性が不足することも。施工を業者に依頼する場合は、彼らがどのような建築知識を持っているか、不足する知識を補う専門家同士の連携を持っているかなどを見極めることが大事です。
依頼者や賃貸利用者も、こうした違いを知っておくことで、建物を見る目が養われ、交渉力も高まります。提案されてくる設計図や賃貸物件にも差が出てくるかもしれません。
📌一般住宅建築士はいわば、「街のお医者さん」。構造・耐震の「専門医」ではない。
最後に―読後に変わる“建物の見え方”
『教養としての建築』は、家を建てる人にも、賃貸で暮らす人にも、「命を守る空間をどう選ぶか」という視点を与えてくれる一冊です。安全リテラシーを高めてくれます。
- 家を建てる人には「どんな設計者を選ぶか」の指針を
- 賃貸派には「どんな建物を選ぶか」、賃貸物件の安全性を見極める力を
本記事では、「建築のダークサイド」をメインに紹介しましたが、本の後半では、建築の未来や最新技術にも触れられており、専門的でありながら日常感覚で理解できる構成も魅力です。
建築は専門家だけのものではなく、「暮らすすべての人の教養」である。
この一冊が、その気づきを与えてくれるはずです。
いつでも解約可能