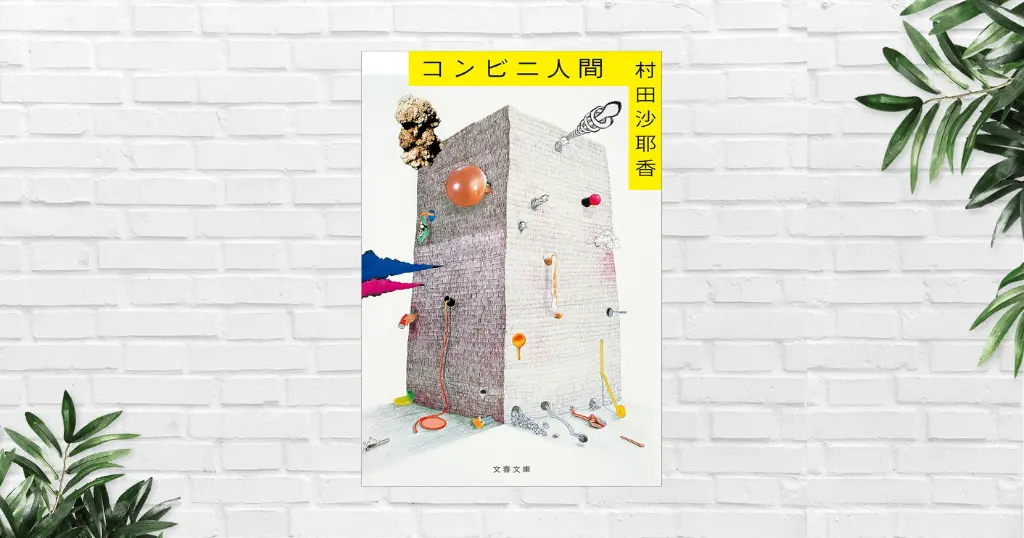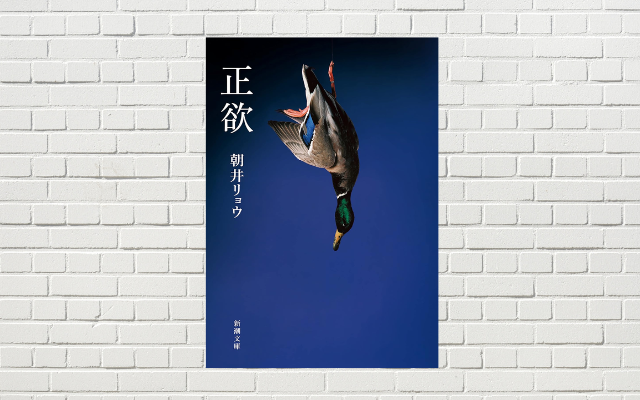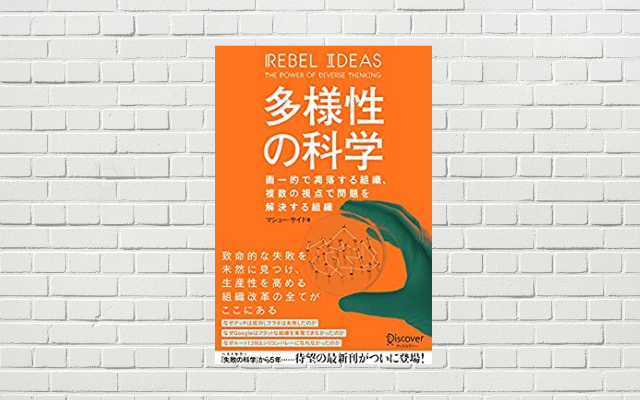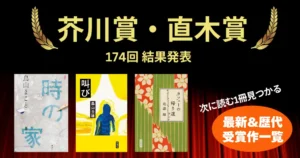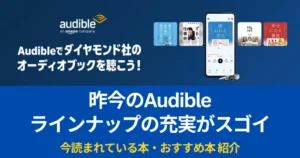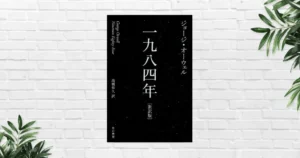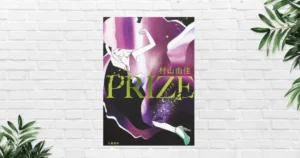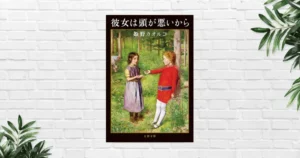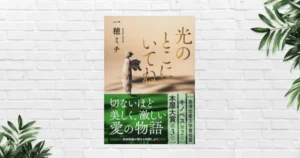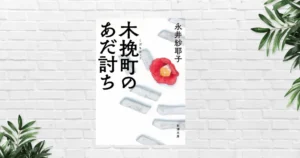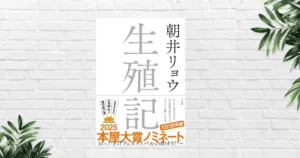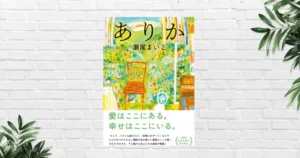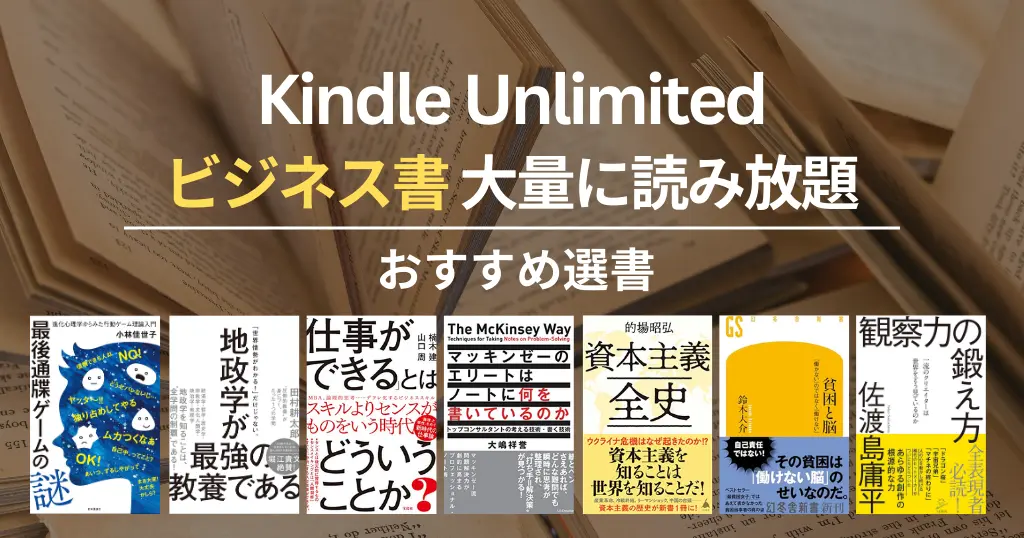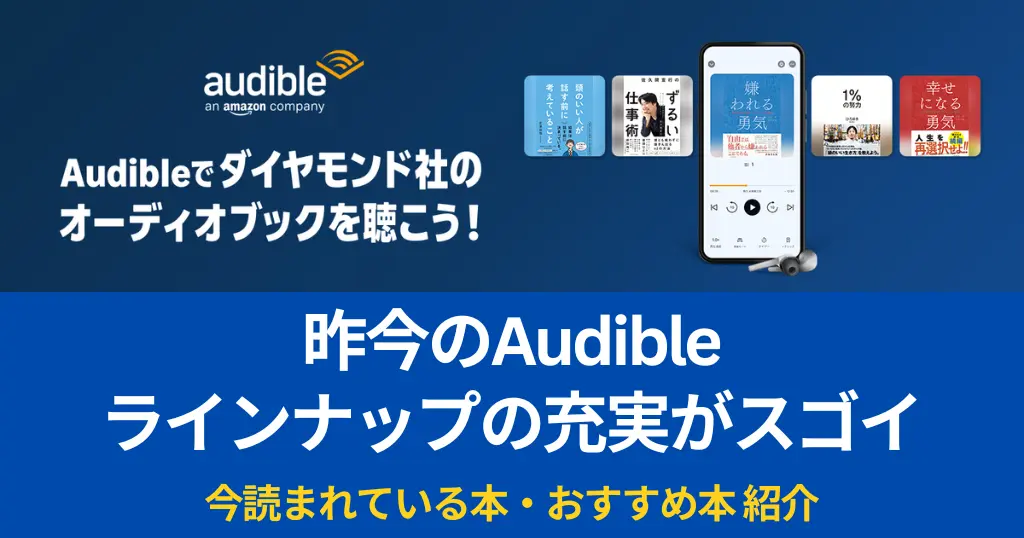- 「普通」を押し付ける社会の息苦しさを、身近なコンビニを舞台に軽やかに描く。
芥川賞受賞のベストセラー。 - 主人公は古倉恵子。36歳、就職せず、18年間、コンビニ バイトで生計を立てる。ある日、バイト先に、社会不適応者のクズ男性がやってきて、恵子に「世間が認める普通」を手に入れるための「便宜的な結婚」を持ちかける。それを受け入れ、同棲を始めた恵子が気づいたことはー
- 「年齢に応じた適切な生き方をしない者」を許さない社会の不寛容さを鋭く描く。作品は、「普通とは何か」「自分らしく生きるとは」という問いを読者に突きつける!
★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本 Audible聴き放題対象本
『コンビニ人間』ってどんな本?
【Kindle Unlimited】30日体験無料
【Audible】 30日間無料体験
【Music Unlimited】30日間体験無料 → 音楽に加え、月1冊Audible読み放題
※3つともいつでも解約可能
現代社会につきまとう息苦しさ。みんなと同じ、つまり、普通でないと、変な人・不快な人のレッテルを貼られます。
社会は男性差別・性的マイノリティなど、「多様性」を受け入れる時代に向かっていると言われますが、現実はそうではありません。
異質を排除する「普通圧力」の存在を、コンビニエンスストアという現代社会に欠かせない場所を舞台にして描いた作品が、村田沙耶香さんが2016年に発表した小説「コンビニ人間」です。
異質なものを排除したいという感情は、人間が集団生活を始めた古代より存在する感情です。これは、決してなくならない「人間の本能」です。
本作は、「普通とは何か」を鋭く問いかけます。さらに、読者は「生き方・働き方の多様性」「自分らしく生きるとはどういうことなのか」を問われます。
第155回芥川賞受賞作、世界各国でベストセラー。私は歴代の芥川賞歴代受賞作品を読み漁ってきましたが、その中で「読んでよかった芥川賞トップ3」に入る推し本です。きっと、あなたも、本作を読めば、その理由に納得できるはずです。
コンビニ人間:あらすじ

主人公の古倉恵子は36歳の女性。大学在学中から18年間、同じコンビニでアルバイトを続けて生計を立てています。
日々の食事はコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、清潔なコンビニの風景と「いらっしゃいませ!」の掛け声が、毎日の安らかな眠りをもたらしてくれると感じています。
彼女は幼いころから「普通」とは違った価値観・感性をもった、いわゆる「変わり者」。周囲の人々と「普通」であることが難しく、自分の奇異な行動が周囲を困惑させたり、怒られる原因となることを幼くして自覚していました。そして、「本当の自分」を内に閉じ込めて成長した結果、社会に上手くくなじめす、社会人となりました。
恵子にとって、マニュアルに沿った言動を取ることを求められるコンビニは、自分が「普通の人」でいられる居場所。コンビニの仕事を完璧にこなし、店のリズムと一体化することで生きがいを見出していました。
しかし、周囲の人々はそんな彼女を不思議がります。特に、特に家族や友人は「いい年をして、彼氏もなく、結婚もできないまま、アルバイトのままでいるのはおかしい」と彼女を心配します。
そんな中、コンビニに白羽という新しいバイトの男性が入ってきます。白羽は社会不適応者で女性蔑視の発言を繰り返し、仕事もまともにこなせない人物です。当然、バイトも首になりますが、そんな無職のクズ・白羽と恵子は再開します。
そんな彼が、「普通」の生き方を手に入れるために、恵子に「便宜的な結婚」を持ちかけます。恵子は「世間が認める普通」を手に入れるために白羽との同居を始めます。そして、白羽が原因で、恵子はコンビニ店員を辞め、就職活動を始めるのですが、その過程で、恵子は自分が本当に求めているものが何なのかに気づき、ある決断を下すのです。
コンビニ人間:感想 ※ネタバレ含む

本書は、白羽のクズ男ぶりなど、物語として面白い。しかし、それ以上に、読みながら考えさせられるのが、「普通とは何か」です。
異物に容赦ない「普通の人」
現代社会は、差別などのない「多様性のある社会」へ進んでいる部分もありますが、それはごく一部。リアルの社会は多様性に寛大ではありません。特に自分の身近にある「異質」には厳しい。例えば、「独身」「無職」など、「年齢に応じた適切な生き方をしない者」を許さない「圧力」が存在します。
本作は、このような「普通」を良しとし、「異質」を排除しようとする強い圧力の存在を、コンビニという身近な舞台を通じて描き出します。
主人公の恵子は、「社会の歯車」の一つとして機能することに幸せを感じています。彼女にとって、コンビニは生きるためのシステムそのものであり、そのリズムに自分を合わせることで安定を得ています。しかし、彼女の生き方は周囲から理解されず、「普通ではない」と判断されてしまします。
一方、白羽は、「普通」に執着しながらも、社会から浮いてしまう矛盾した存在です。彼は女性蔑視的な発言をしながらも、結婚という形で社会的な安定を求め、恵子を利用しようとします。しかし、恵子にとって白羽との関係は「普通」を装う手段にすぎず、最終的には彼を見限ります。
現代の日本社会では、大卒・正社員・結婚といったライフステージが「普通」として求められがちです。しかし、それとは異なる価値観を持つ人々も存在します。そうした人々が生きづらさを感じる社会の構造が、この作品を通じて浮き彫りにされています。
「現代社会の息苦しさ」がテーマながら、読み口は軽やか
本社は、「普通とは異なる価値観を持つ人の生きづらさ」という重いテーマを扱っていますが、ストーリーがとても軽やか。軽やかなのに、「普通とは何か」を読者に鋭く問いかけます。
本作を読みながら、描き方が大局的だと感じたのが、朝井リョウさんの「正欲」。変わった性癖を持つマイノリティが社会で生きる息苦しさを描いた作品ですが、「異質者」の生きづらさを、極めて重たく描いています。合わせて読みすると面白いと思います。
多様性については、シュー・サイドさんのベストセラー『多様性の科学』を読んでおくことをおすすめします。
異質を見下す社会
「コンビニ人間」は、「異質な人を見下す人間の姿」も浮き彫りにしています。
人には「嫌い」という感情があります。厄介な感情ですが、中野信子さんの『「嫌いっ!」の運用』によると、「嫌い」は脳に備えつけの重要なアラーム機能であり、無視し続けると、ストレス・ウツとなるので、「嫌いの感情」を無視してはいけません。
しかし、この”嫌い”が「集団圧力」「同調圧力」で作用すると、集団内で「違う人」を見下し、「制裁」「排除」する力が働くようになります。困ったことに、このようなバイアスは、助け合いがより大事になる戦争や不況など、社会が不安になるとさらに悪化します。それは、誰か悪者を作った方が精神が安定するし、また、収入減少でで下がる自己評価を埋め合わせるために「自分&自分の属する集団は優秀に違いない」と、根拠なく下駄を履かせようとするからです。
現代はこのような「異質者の見下し・排除」は至る所に存在しています。本作は、何気ない日々の生活の中に、「無自覚に犯してしまっている見下し」があることを、気づかせてくれます。
コンビニ人間:「はっ」とさせられたフレーズ

「コンビニ人間」を読んでいると、無意識に陥っている「偏見」にハッとさせられます。この気づきを忘れないために、心に引っかかったフレーズを抜粋して紹介します。
「異質者」に無意識に行われる「見下し」
同じことで怒ると、店員の皆がうれしそうな顔をすると気が付いたのは、アルバイトを始めてすぐのことだった。店長がムカつくとか、夜勤の誰それがサボってるとか、怒りが持ち上がったときに協調すると、不思議な連帯感が生まれて、皆が私の怒りを喜んでくれる。
泉さんと菅原さんの表情を見て、ああ、私は今、上手に「人間」ができているんだ、と安堵する。この安堵を、コンビニエンスストアという場所で、何度繰り返しただろうか。
興味深いので私は見下している人の顔を見るのが、わりと好きだった。(略)
何かを見下している人は、特に目の形が面白くなる。そこに、反論に対する怯えや警戒、もしくは、反発してくるなら受けてたってやるぞという好戦的な光が宿っている場合もあれば、無意識に見下しているときは、優越感の混ざった 恍惚 とした快楽でできた液体に目玉が 浸り、膜が張っている場合もある。
差別する人には私から見ると二種類あって、差別への衝動や欲望を内部に持っている人と、どこかで聞いたことを受け売りして、何も考えずに差別用語を連発しているだけの人だ。白羽さんは後者のようだった。
店長は、使える、という言葉をよく使うので、自分が使えるか使えないか考えてしまう。使える道具になりたくて働いているのかもしれない。
「普通」であるために
あ、私、異物になっている。ぼんやりと私は思った。(略)
正常な世界はとても強引だから、異物は静かに 削除される。まっとうでない人間は処理されていく。そうか、だから治らなくてはならないんだ。治らないと、正常な人達に削除されるんだ。(略)
家族がどうしてあんなに私を治そうとしてくれているのか、やっとわかったような気がした。
皆が不思議がる部分を、自分の人生から消去していく。それが治るということなのかもしれない。
ここ二週間で 14 回、「何で結婚しないの?」と言われた。「何でアルバイトなの?」は 12 回だ。とりあえず、言われた回数が多いものから消去していってみようと思った。
縄文時代から社会は「独身」「無職」に容赦ない
皆、変なものには土足で踏み入って、その原因を解明する権利があると思っている。私にはそれが迷惑だったし、 傲慢で鬱陶しかった。
白羽さんの言うとおり、世界は縄文時代なのかもしれないですね。ムラに必要のない人間は迫害され、敬遠される。つまり、コンビニと同じ構造なんですね。コンビニに必要のない人間はシフトを減らされ、クビになる(略)
コンビニに居続けるには『店員』になるしかないですよね。それは簡単なことです、制服を着てマニュアル通りに振る舞うこと。(略)普通の人間という皮をかぶって、そのマニュアル通りに振る舞えばムラを追い出されることも、邪魔者扱いされることもない。
ムラのためにならない人間には、プライバシーなんてないんです。皆、いくらだって土足で踏み込んでくるんですよ。結婚して子供を産むか、狩りに行って金を稼いでくるか、どちらかの形でムラに貢献しない人間はね、異端者なんですよ。
だから現代は機能不全世界なんですよ。生き方の多様性だなんだと綺麗ごとをほざいているわりに、結局縄文時代から何も変わってない。少子化が進んで、どんどん縄文に回帰している、生きづらい、どころではない。ムラにとっての役立たずは、生きていることを 糾弾 されるような世界になってきてるんですよ。
最後に
今回は、村田沙耶香さんの小説「コンビニ人間」のあらすじ。感想を紹介しました。
感想には述べませんでしたが、ラストに向かうシーンもとてもいい。恵子が「「自分がイキイキできる、自分の居場所(働く場)はココだ!」と気づく過程は、ビジネスマンなら何か感じるところがあるはずです。自分の生き方・働き方も考えさせられます。
いい小説です。一人でも多くの方に読んでほしいです。
文学賞受賞作には、読んでおきたい良い作品が色々あります。歴代芥川賞・直木賞受賞作もチェックしてみて下さい。