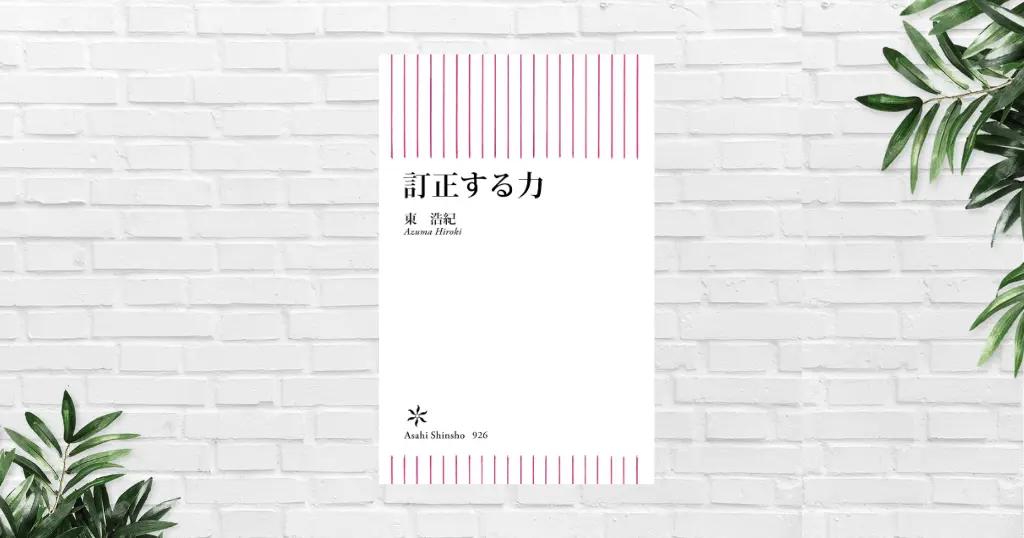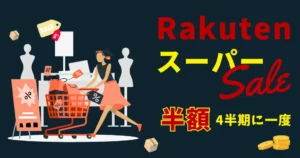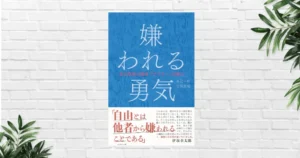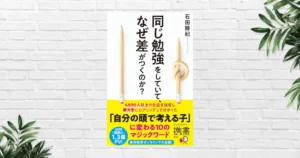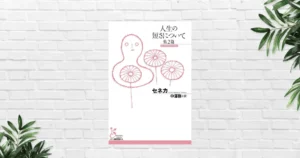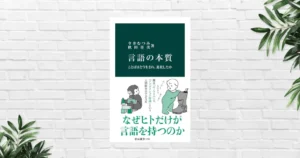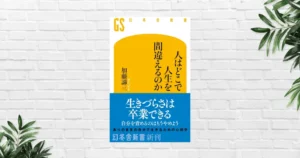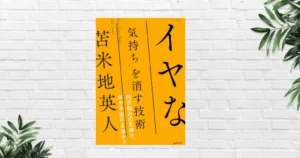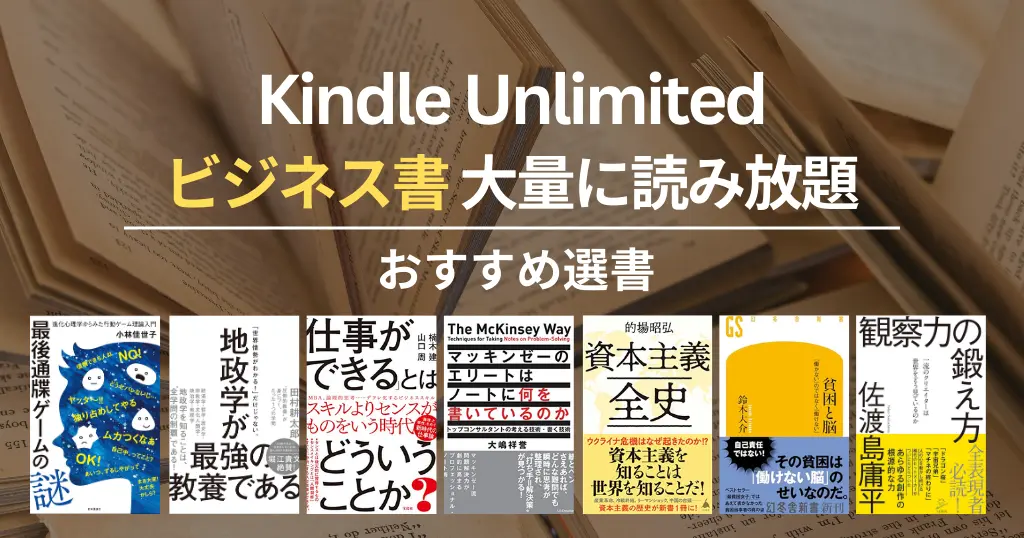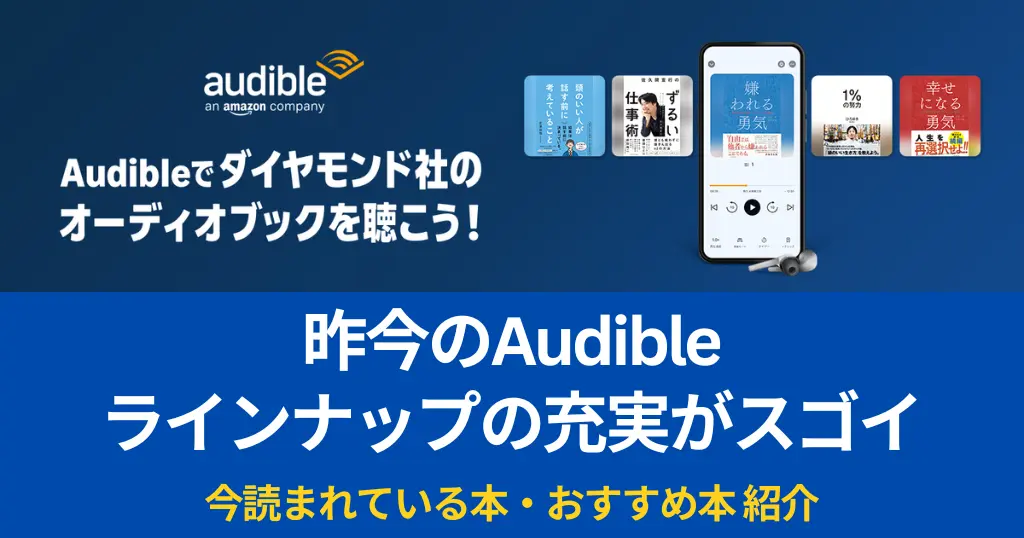- 誤ることを前提に、どう訂正するかー
人も社会も誤るし、未来永劫続く固定された「正解」もない。成長とは訂正の積み重ね。過去の再解釈により、訂正を重ねる姿勢が人を、社会をよりよくする。 - 日本社会を縛る「空気」の支配
空気が優先され、誤りや矛盾が訂正されにくい日本。空気を壊すことへの恐れが、変化のスピードについていけない社会構造を生んでいる。 - 「リセット」ではなく「訂正」の積み重ね
全面リセットは、新たな矛盾を生む。本当に持続可能な変化は、過去を再解釈しながら少しずつ訂正していく営みから生まれる。社会改革や生活習慣の改善まで幅広く応用できる知恵!
★★★★★ Audible聴き放題対象本
『訂正する力』ってどんな本?
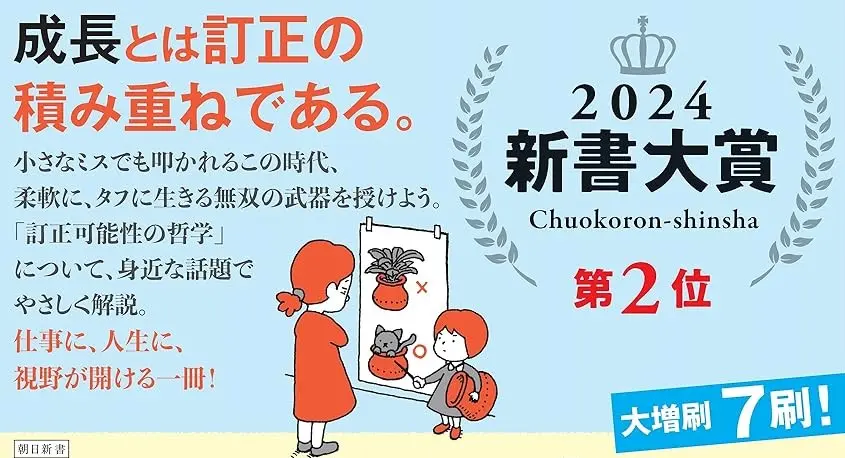
SNSの普及によって、誰もが自由に発言できる時代になりました。
しかしその言論空間は、自由と引き換えに「炎上」「断罪」「分断」が日常化する場にもなっています。
過去の発言は永久保存され、謝罪や訂正は「負け」とみなされる。
表現の一部を切り取って揚げ足を取るような批判も後を絶たず、
発信者は誤りを認めるよりも、相手を攻撃することで自らを守ろうとする――そんな空気が蔓延しています。
これでは個人も社会も、前向きに進んでいくことはできません。
『訂正する力』は、こうした現代社会に一石を投じる一冊。『新書大賞2024』では2位に輝く良書です」。
著者の東浩紀さんは、「人間も社会も誤る」という前提に立ちます。そのうえで、過去を否定するのではなく、再解釈しながら「変えていく=前進していく」ことこそ、民主主義を持続させるために大切だと論じます。
単なる道徳論ではありません。
むしろ、社会制度や歴史、哲学的思考を踏まえた上で、日常の意思決定や人間関係、社会参加にまで応用可能な「よりよく生きる知恵」を与えてくれます。
『訂正する力』が投げかける問い
自分を高め、社会を良くしていくには「よい変化」が必要です。
最初は「最適解」だったものも、時とともに適合しなくなることはよくあります。
それをより良い状態にするためには、「過去を訂正する力」が欠かせません。
「訂正」できない弊害
- 人間の言葉や判断には必ず誤りが含まれる。
- 重要なのは「誤りを前提とした言論の仕組み」をどう設計するか。
- 訂正が可能な社会は寛容で開かれているが、訂正できない社会は硬直し、全体主義へと近づいてしまう。
「空気」が訂正を阻む
日本は変化しにくい国と思ったことはありませんか?
それは訂正できないから。日本社会において、訂正を困難にしている最大の要因は「空気の支配」です。
- 明文化されたルールよりも、その場の雰囲気や暗黙の了解が優先される。
- 間違いや矛盾があっても、「空気を壊す」ことを恐れて指摘されない。
- その結果、「どうせ言っても変わらない」という諦めが広がり、空気の支配がますます強まる。
コロナ禍におけるマスク着用の長期化なども、この「空気の強さ」が影響していたと著者は指摘します。
空気を優先する社会では、明らかな誤りや不合理もそのまま流されてしまう。これでは、変化の速い社会に適応できなくなります。
学びと気づき
私が本書を通じて得らた最大の学びは、次の点です:
本書のポイント:私の気づき
- 人間も社会も合理的には動かない
人も社会も非合理である。間違えないことより、間違いの訂正。 誤りを前提にした制度設計が必要。 - 「正しさ」は変わる
固定された「正解」はない。過去の再解釈により、訂正を重ねる態度が健全性を高める。 - 論破ではなく訂正を許容する空間
過ちを糾弾するのではなく、建設的に「どう訂正していくか」を共有することことが大事。 - 過去から地続きでないものは定着しない
「リセット」ではなく「訂正の積み重ね」が大事 - 寛容と成熟
個人も社会も、「誤りをどう扱うか」に成熟度が表れる。
❸~❺に関わって、重要になるのが「リセット」と「訂正」の違いです。
「リセット」と「訂正」の違い
なぜ、「リセット」ではなく「訂正の積み重ね」が大事なのでしょうか。
- 「リセット」の発想:ゼロからやり直す思想
- 過去を全面否定し、新しい社会を一気に築こうとする(例:フランス革命、ソ連の共産主義革命)。
- 急進的で分かりやすいが、人間の誤りを無視しているため、必ず新たな矛盾を生み、独裁や抑圧に転じやすい。
- 「訂正」の発想:積み重ねて修正していく思想
- 人・社会は誤ることを前提に、改善・修正の積み重ねて、社会をより良い方向に進める。
- 過去の価値や知恵を残しつつ、少しずつ変化させる。
- 過去と現在の連続性を保つことで、安定的に社会を更新できる。
この思想は、社会改革だけでなく、組織運営や、健康習慣・読書習慣など、個人の生活習慣でも同じです。
全面否定の「リセット」では人々はついてきません。
「一気に変える」のではなく、過去を再解釈しながら「少しずつ修正する」ことで、変化は定着するのです。
最後に
『訂正する力』は、『新書大賞』の上位入賞作にふさわしい本で、多くの「よりよく生きる知恵」「よりよい社会を生きる知恵」を与えてくれる1冊です。
私たちがどれほど「誤りに不寛容」であり、「空気に従属しているか」を静かに問いかけ、
また、過去を否定するのではなく、再解釈しながら前に進むという、成熟した変化のあり方を示してくれました。
SNSや政治、教育、ビジネス、そして日々の人間関係にまで通じる、普遍的かつ実践的な知恵でもあります。
いまを生きる私たちに必要なのは、完璧さではなく、訂正を重ねる勇気。
訂正の積み重ねが成長につながる!
本書は訂正する勇気を、確かに授けてくれます。是非、手に取って読んでみることをおすすめします。
いつでも解約可能