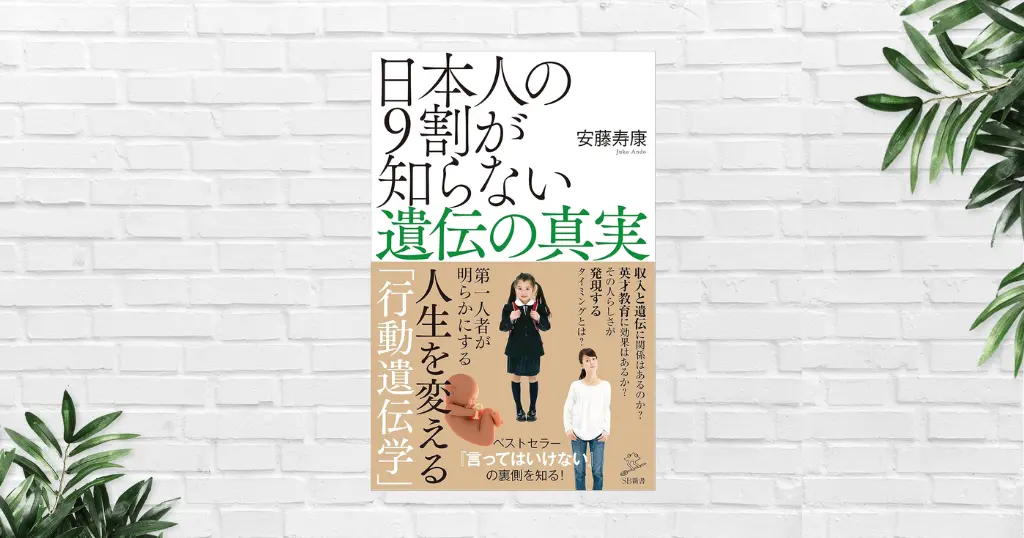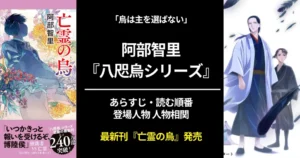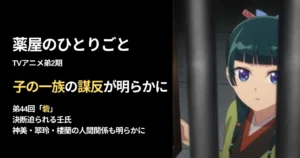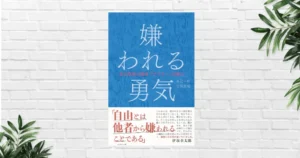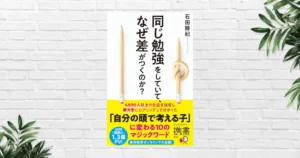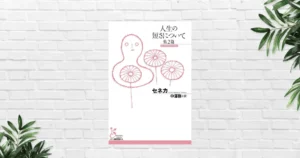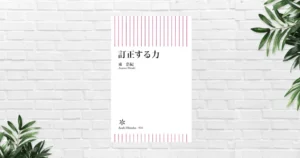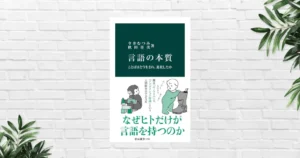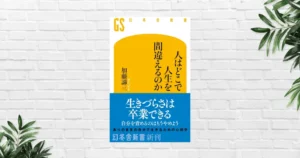- 教育は「才能を引き出す場」であるべき
知能・能力に対する遺伝子の影響は確かに大きい。だが、開花させるのは、環境と経験の力。
本書は、子ども一人ひとりの内なる芽を見つけて伸ばす教育の重要性を説く。 - 「考える力」は命令で育たない
「考えろ」という教育は逆効果。大切なのは、知識欲=エロスを刺激し、自然な好奇心から思考を深める環境づくり。 - 遺伝的個性を活かす社会へ
遺伝の差を受け入れ、個人の得意を伸ばす「キッザニア的社会」を提唱。多様な才能が活きる教育と社会のあり方を描く。
★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本
『日本人の9割が知らない遺伝の真実』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】 最初の30日間体験無料🔥 ※対象者限定で「あなただけの特別プラン」も
私たちはこれまで、「努力すれば夢は叶う」「環境を整えれば誰でも伸びる」
そんな前提で生きてきました。
でも、それはすべての人に当てはまるのでしょうか?
安藤寿康さんの『日本人の9割が知らない遺伝の真実』は、こうした素朴で根本的な問いに、「行動遺伝学」という科学的な視点から答える一冊です。
学力、収入、性格、才能……実はその多くが「遺伝」で決まっている。
私たちが「努力の成果」と信じていたことの多くは、実は“生まれつき”の素質によるもの。
——残酷ですが、これは紛れもない科学的な事実です。
しかも、学校は「才能を育てる場所」ではなく、「才能の差があらわになる場所」である——
と、なんとも、衝撃的な指摘で、私たちが信じてきた「教育の平等神話」を大きく揺さぶります。
しかし、それは決して「遺伝で決まるから、努力は無意味」という絶望を説くものではありません。
社会には、遺伝的才能を活かす“居場所”がある。
才能のない場所で努力するより、自分に合った場所で力を発揮するほうが、ずっと合理的で幸せになれる。
人の持つ能力は実に多様。そのことに気づいて、動き出そうというと、光を与えるのです。
「できないこと」より「できること」。
本書は、自分の中にある能力を見直し、その能力を使って「どう生きるか」を考えるきっかけを与えてくれます。
「頑張っているのにうまくいかない」と悩んでいる人はもちろん、子どもの教育をどうしたらいいかと考える親御さんにもおすすめです。
「頭がいい」とは?──私たちが見落としている“頭の良さ”の正体

「頭がいいとは?」と問われた時、あなたは何と答えますか?
テストの点数?仕事の処理能力?それとも、物事を論理的に考える力でしょうか。
実は、「頭の良さ」とは、絶対的な基準があるものではありません。時代・社会の変化に応じて変化する曖昧なモノなんです。
産業革命が変えた、頭の良さ
従来の社会で生きていくためには、手の届く狭い経済圏の中の「具体的なもの・こと」が大事でした。
人の能力で言えば、例えば「パンがうまく焼ける」といった具体的な技能が求められました。
しかし、これが大きく変わったのが「産業革命」。
社会のあり方が変わり、世界はつながり、「金融」「法の支配」「人権」など、目に見えない抽象的な概念が世界を動かす時代に移行しました。
社会で重視される能力も、手を動かして具体的なものを作る人ではなく、「抽象化思考」のできる人たち。抽象的に物事を考えられなければ、組織の上に立つこともできなくなりました。
ここで大事なのは、「頭の良さ」や「重視される知能・能力」は、時代や社会と共に変化するということです。
「○○力」ブームの背景にあること
学校のテストや知能テスト。これらはいわば、現代において、大事とされる「知能」を数値で測るものです。
今の世の中で必要とされる「知能・能力」とも言えます。
しかし、社会における人間の能力は、はるかに多様で測りきれないものです。
例えば、「道路工事を効率よく進める力」や「誰とでもすぐに打ち解ける力」なども、本来は社会にとってかけがえのない「知能」のひとつです。
近年、「○○力」(コミュ力、女子力、転職力…)といった言葉が溢れている背景には、「知能とは何か」が再定義されつつある社会の兆しが見て取れます。
あなたの持つ、人と違う能力も、ただ、世の中的に、まだ正しく価値が評価されていないだけかもしれません。
「親ガチャ」は本当か?――遺伝と才能の、知られざる真実

「親ガチャ」という言葉があります。
どんな親のもとに生まれるかは運次第——この言葉には、遺伝への諦めが込められているようにも感じます。
しかし、著者は言います。
遺伝子の影響は確かに大きい。だが、それを発現させるのは、環境と経験の力であるー。と
親ガチャを紐解く
「親ガチャ」 という言葉を遺伝的に分解すると、以下の2つの「運」が関わっています。
- 遺伝子の組み合わせは完全にランダム ⇒「遺伝子ガチャ」
- 両親から半分ずつ遺伝子を受け継ぐが、そのどの遺伝子を受け継ぐかは偶然
- たとえば、背の高い両親から生まれても、自分がその「高身長の遺伝子」をもらえるとは限らない
- 育つ環境も親によって決まる ⇒ 「環境ガチャ」
- 収入、教育方針、住む地域、生活習慣、価値観など、生まれた家の環境は子どもの成長に大きく影響
- 同じ遺伝子を持っていても、環境が違えばまったく違う人生に
これらが、どのように人の人生に影響するかは、特性によって異なります。
IQ・認知能力は、想像以上に「遺伝」に左右されます。
それは、遺伝がスタートラインの差、能力の下地となるからです。
| 項目 | 遺伝ガチャの影響 | 環境ガチャの影響 |
|---|---|---|
| 身長・体型 | 大きい | 中程度(栄養など) |
| IQ・認知能力 | 中〜大 | 大 |
| 性格傾向(外向性・神経質など) | 中 | 中〜大 |
| 学歴・収入 | 小〜中 | 非常に大 |
大事なのは「遺伝子の発現」
優れた遺伝子を持っていても、才能が開花するとは限りません。
才能は、「持っていること」よりも、「開花させること」(遺伝子の発現)のほうがはるかに重要です。
遺伝子のスイッチをONにする鍵は、親の働きかけや、偶然の出会い、そして多様な経験のなかにあります。
たとえば、同じ親の元に育った姉妹がバイオリンを習っても、それを「好きになってのめり込むか」は、子ども自身の遺伝的素質と、本人だけの経験=非共有環境によります。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 遺伝子 | 能力の“タネ”を持っているかどうか |
| 遺伝子の発現 | 環境や経験によって“タネ”が芽を出すかどうか |
時間が経つほど、環境よりも遺伝の影響が表面化する
親が東大卒なら、子も頭がよく、収入も高くなりやすい。
確かにこれは事実です。しかし、ある研究によれば、親の資産の学歴のような「共有環境」の影響は50%。
思っている以上に影響が少ないのです。
子ども時代は「親の育て方」「家庭環境」といった共有環境の影響が大きいです。
しかし、人になるにつれて、人は自分の意思で環境を選ぶようになっていきます。
その選び方に、もともとの遺伝的な傾向(性格・能力・興味)が大きく影響するため、結果的に「遺伝の影響が強く見える」ようになっていくのです。
また、女性では、収入に遺伝の影響がほとんど見られません。
このことは、「女性の潜在能力は、社会の中で十分に活かされていない(高給な職種につくことが難しい)」という環境の影響を浮かび上がらせています。
“正しい教育”とは何かを問い直す

なぜ、教育は格差を拡大してしまうのか?
現在の学校教育には、ひとつ大きな前提があります。それは「努力すれば頭はよくなる」という考え方です。
けれど、実際には「記憶力」「読解力」「論理的思考力」などには、生まれつきの得手不得手があり、それを無視した教育は、不得意な子どもに“無理な努力”を強いることになります。
すると学校はどうなるか?
できる子はどんどん伸び、そうでない子は苦しみ、結果として“格差を広げる装置”になってしまうのです。
不得意な分野でいくら頑張っても芽が出ない。そんな経験、誰にもありますよね。
でも、それは「才能がない」からではなく、その子が持っていたのは「別のタネ」かもしれません。
それを見つけて育ててあげるのが、本当の教育です。
子どもの“芽”を見つけ、引き出す教育へ
私たちはつい、教育を「白紙の脳に知識を書き込むこと」と考えがちです。
でも、もっと大切なのは、「すでにその子の中にある才能や個性をどう引き出すか」という視点です。
不得意なことを無理やりやらせるのではなく、得意なこと・好きなことを見つけて伸ばす。
親や教師に求められるのは、子どもの「芽」を見つけ、光を当て、育ててあげることです。
「考える力」という幻想――本当に必要なのは“知識欲”の刺激
「努力」と同様に、最近の教育では「考える力を育てよう」というスローガンがよく掲げられています。
でも著者は、それをただの“思考停止ワード”だと厳しく批判します。
なぜなら、「考える力」は、誰かに言われて鍛えられるものではないからです。
人は、自分の好奇心や興味を通して、自ら考えるようになるのです。
つまり、本当に大切なのは「考えさせる」ことではなく、「知りたい!」「やってみたい!」というエネルギー=知識欲をどう刺激するか。
この“知識欲”は、古代ギリシャの哲学者プラトンが語った「エロス(=渇望)」と同じもので、「不完全な自分が、よりよいものを求めて上へ向かう力」なのです。
教育の原点とは、この「エロス=知識欲」を育てることにあります。
人の能力は多様。遺伝を受け入れた社会へ
すべての子どもが力を発揮できる教育の1提案
著者は、「すべての子どもが力を発揮できる教育」の姿として、社会の「キッザニア化」を提案します、
つまり、子どもが実際の仕事や社会を体験できる機会を増やし、「好き」や「得意」を早く見つけられるようにするのです。才能の芽が出たら、すぐに“実践の場”を与える。
これは、現代の教育に欠けている視点かもしれません。多くの人が、自分に向いている仕事、あるいは、「絶対的に得意」ではなくても、「相対的にマシ」な分野――比較優位を見つけて、そこで自分の立ち位置を作る自分の才能を活かすことができれば、個人はもちろん、社会全体が受けるメリットも大きくなり、皆の幸せにつながります。
そうした比較優位で生きるなら、グローバルな競争社会よりも、顔の見える地域コミュニティのような場所の方が合っているかもしれません。昔ながらの「具体的な世界」に、自分の居場所を作るのです。
「多様な才能」が認められる社会へ
テクノロジーの進化により、これからは求められる能力がどんどん多様化していきます。
つまり、これまで評価されなかったような能力に光が当たる時代が来るということです。
大切なのは、「能力」とは社会が定義するものだということ。
社会の価値観が変われば、今まで目立たなかったあなたの才能が、いつか主役になるかもしれないのです。
最後に
今回は、安藤寿康さんの『日本人の9割が知らない遺伝の真実』からの学びを紹介しました。
遺伝を「才能の格差」として卑下するのではなく、そこに「人間の能力の多様性」を認め、それを活かそうとする提案に、明るい光を見ました。
努力は意味がない? いいえ、それは違います。
「正しい方向」に努力すれば、私たちはもっと自由に、自分らしく生きられる。
この本は、そうも教えてくれます。
「頑張ってもうまくいかない」と悩む人に、
「子どもの才能を伸ばしたい」と願う親に、
そして、「自分の可能性に気づきたい」すべての人に—— ぜひ手に取ってみて下さい。