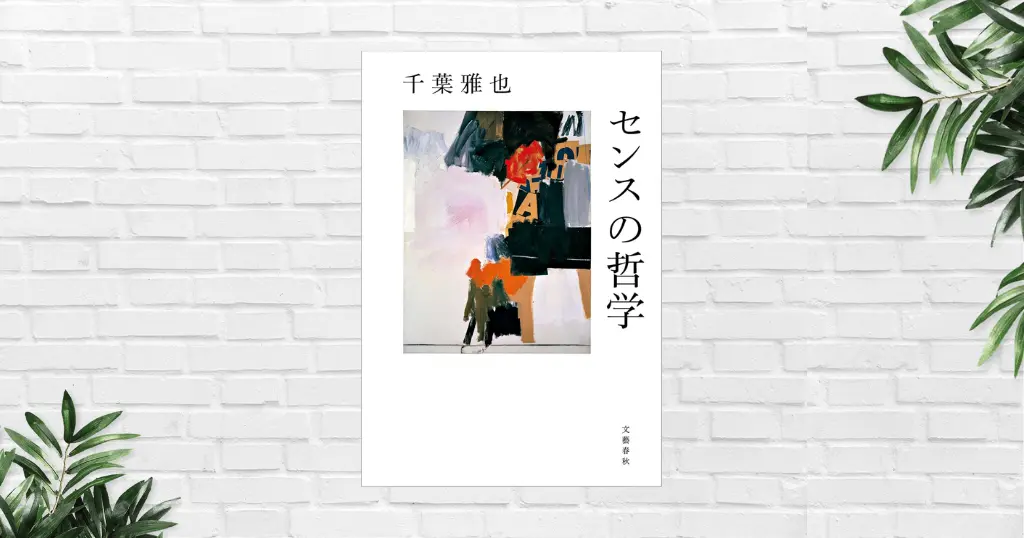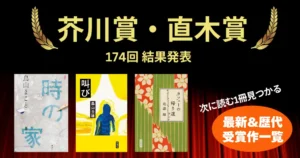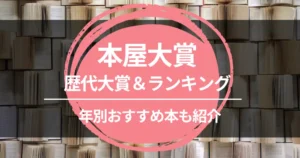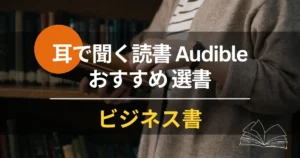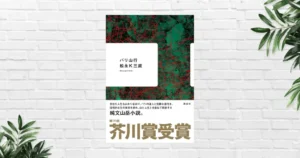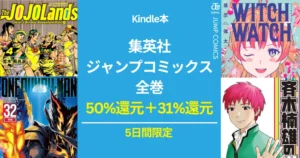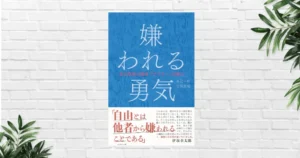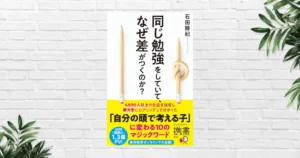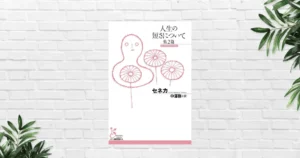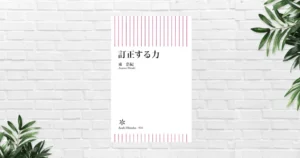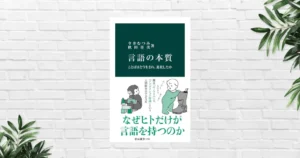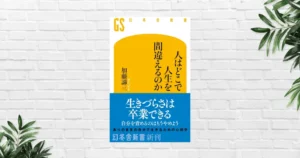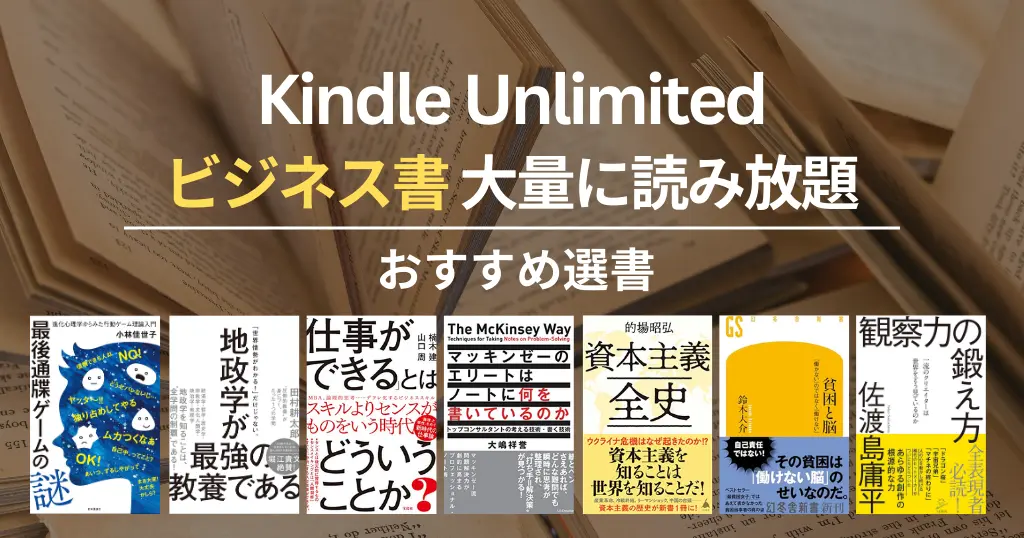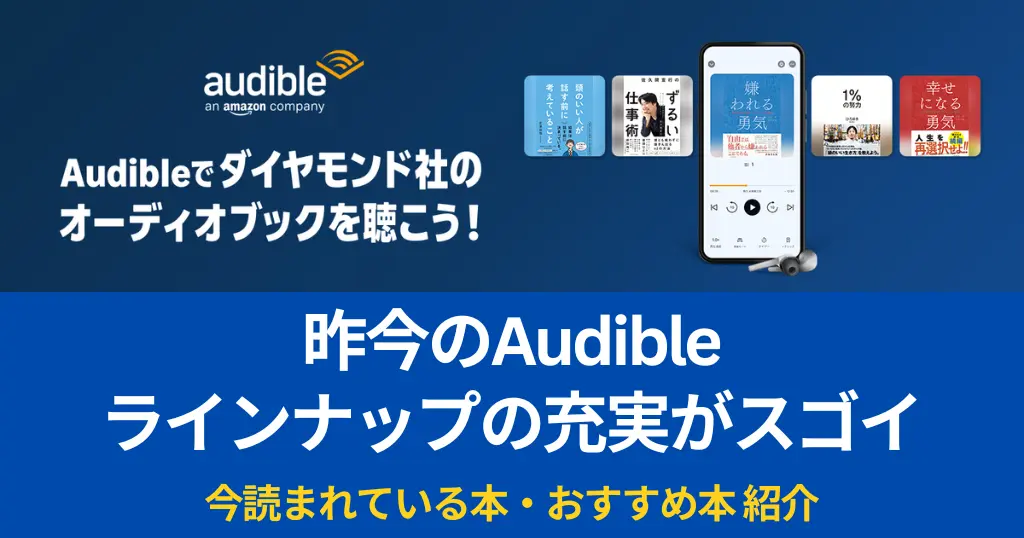- 「センス」は鍛えられる——哲学的実践としてのセンス論
センス=直観的で総合的な判断力。生まれ持ったものではなく、誰でも育てて広げられる。この「センス」の構造を、哲学的視点から丁寧に紐解き、実践的に伸ばす方法を提示する。知的刺激に満ちた一冊。 - 日常と哲学を架橋する、現代的思考のスタイル
ファッション、美術、音楽、文学、日常生活──あらゆるジャンルを横断しながら、「センスとは何か?」を深く掘り下げる。 - 「生き方のスタイル」を考えるヒントに
独自のセンスを磨くには、「ズレ」と「味」が大事。自分らしさをどう保ち、更新するか。センスをめぐる思索は、生き方そのものを問い直す手がかりとなる。
★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本 Audible聴き放題対象本
『センスの哲学』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】30日体験無料
【Audible】 30日間無料体験
【Music Unlimited】30日間体験無料 → 音楽に加え、月1冊Audible読み放題
※3つともいつでも解約可能
「あの人はセンスがいい」「このデザイン、センスないなぁ」──。私たちは日常会話の中で、何気なく「センス」という言葉を使っています。
本書『センスの哲学』は、「センス」という言葉の本質に哲学的に迫りながら、仕事や日常生活の中で活きる「自分らしい独自センス」を育てるヒントを与えてくれる一冊です。
「センス、悪っ」──。この言葉にグサリと刺さる痛みを覚えるのは、センスが単なる好みの問題を超えて、人格全体への評価のように響くからです。センスは「生まれつきの才能」であり、努力ではどうにもならない――そんな思い込みが、私たちの中にあります。
しかし著者・千葉雅也さんは、そうしたイメージを軽やかに覆す!センスとは「直観的で総合的な判断力」であり、「感覚」と「思考」を結びつける力。生まれつき備わったものではなく、「多様な経験」と「自分なりの選択・表現」を通じて育てられるものだと説くのです。
このセンスを育てる鍵となるのが「文化資本」の形成。多くのものに触れ、鑑賞し、体験を重ねること。そして、ただ「良いモノ」を模倣するのではなく、自分自身の手触りでものごとを捉えることが、真のセンスにつながると、著者は語ります。
ファッション、美術、音楽、文学、日常生活── さまざまなジャンルを横断しながら、「センスとは何か?」を深く掘り下げる本書。「選ぶ」「感じる」「考える」ことに、新たな視点が加わるはずです。
そして何より、本書の千葉さん自身の語り口や着眼点にこそ、独自のセンスが光ります。そこには、“ズレ”と“味”という、他に代えがたい魅力があります。
自分の「センス」の育て方を見直し、育てたくなる。そんな知的刺激に満ちた一冊です。
センスとは何か

センス=直観的で総合的な判断力。
単なる「感覚」ではなく、「感覚と思考を結びつける力」です。芸術や美的感覚にとどまらず、日常の選択や会話など、センスはあらゆる場面に広がっています。
「センスは育てられる」という視点
「センスがない」と言われると、暗に、「だから何をやってもダメ」というような、人格全体を否定されるような響きを伴います。それは、センスが“生まれつきの才能”とみなされやすいからです。しかし、千葉雅也さんは、それに異を唱えます。センスとは生得的な資質ではなく、「育てることができるもの」だと説きます。
そして本書では、「センスがない状態」を単に否定するのではなく、それを「センスに対して無自覚な状態」と捉え直します。つまり、感覚や選択に意識的になれば、誰もがセンスを磨いていけるということです。
センスは経験と自覚から育つ
センスを育てる鍵は、「文化資本」の蓄積にあります。
つまり、多くのものを見て、聴いて、体験し、味わい、自分なりに解釈する──この繰り返しが、自分の判断軸、すなわちセンスを形作っていきます。
「子どもには多くの体験をさせなさい」と言われるのも、文化資本の土台づくりが重要だからです。とはいえ、それは子ども時代に限られた話ではありません。大人になってからでも、多様な経験を通じてセンスは十分に育ちます。
「再現」から「生成」へ──ズレと味わいを楽しむ感性
センスを磨く過程は、AIがデータを学習し、新しい表現を生み出すプロセスにも似ています。最初は「模倣」でもかまいません。しかし、やがて模倣から一歩抜け出し、「自分自身の表現」を持つことが極めて大事です。
たとえば、絵を上達させるためには模写から始めますが、ただ写実的な絵を描けるようになっても、それだけでは面白みに欠けます。完全な再現にとらわれると、自由さやユーモアが損なわれてしまうのです。
そこで大事になるのが、「ズレ」や「味」の感性です。
たとえば「ヘタウマ」と評される表現には、写実性からの“ズレ”があり、そのズレが独特の魅力やユーモアを生み出します。この「味」が、その人ならではのセンスとなるのです。
つまり、モデルの完全再現ではなく、「自分自身の線の運動」──手触りのある感覚で世界を捉えること。それがセンスを開くカギとなります。
「モデル再現する」ことから降り、自分なりの価値観や表現を持つこと。そこにこそ、本当のセンスの芽生えと広がりがあります。重要なのは、子どものような自由さと、遊び心を忘れないことなのです。
【実践編】日常生活でセンスを磨くには?

ここからは、センスをもっと身近なものとして捉えるために、日常生活と結びつけながら考えていきましょう。
センスを磨く鍵は「リズム」にある
千葉さんは、「すべての芸術はリズムである」と言います。つまり、リズムを感じ取る力こそが、センスを育てる鍵になるというのです。
リズムとは、時間の流れの中にある“凸凹”や“強弱”の配列のこと。強い部分と弱い部分が交互に現れる「並び」によって構成されます。千葉さんは、このリズムを以下の2つに分けて捉えます。
- うねり:変化の流れ
- ビート:存在/不在の切り替え(0→1)
センスとは、この「うねり」と「ビート」の両方を感じ取り、ものごとを捉える力です。
文学に見る「リズム」の違い
本好きの私にとって、特に印象的だったのが「文学のリズム」に関する指摘です。
| ビート」重視の作品 | エンタメや大衆文学。 起承転結が明快で、0/1の展開がはっきりした、ハラハラ・ドキドキの物語展開が魅力。 |
|---|---|
| 「うねり」重視の作品 | 純文学的な作品。 ディテールの厚みや微細な変化を楽しむタイプ。 |
たとえば、芥川賞作品は「うねり」を重視する傾向が顕著です。村上春樹作品もまさにそう。一方、本屋大賞にノミネートされる作品は「ビート」が明確で、展開がわかりやすいものが多いと感じます。
餃子の美味しさも「リズム」芸術?
「リズム感」は音楽や文学だけの話ではありません。千葉さんは、なんと「餃子」にもリズムの芸術があると述べます。
熱っ → パリッ → ジュワッ →その後やってくる、 醤油の塩気 → お酢の酸味 → ラー油の刺激
こうした複数の感覚がセッションし、時間の中で順々に押し寄せてくることで、餃子の“リズム”が生まれます。これは料理だけでなく、美術やファッション、あらゆる表現に通じます。
【ここまでのまとめ】センスとは?センスを磨くとは?
センスについての見方、少し変わってきたのではないでしょうか?
- センスとは:「リズムとして世界を捉える感受性」
- センスを磨くには:「多次元的なリズム配置=マルチトラックの構造」に気づくこと
- 「センスがいい」とは:その構造的な“並び”や“ズレ”を面白く感じ取れる力のこと
つまり、物事の「リズム」を感じ、そこにある奥行きやズレに敏感になること──これが、センスを育てるための第一歩です。
【実践】もっと芸術を楽しむために

私たちはつい、何ごとも効率を優先しがちです。コスパやタイパを重視し、「無駄」を避けたくなります。でも、芸術とはまさに「時間そのものを味わう行為」。効率とは真逆の世界に身をゆだねることが、その本質です。
「無駄に見える時間」をあえて体験する。それこそが、芸術鑑賞なのです。
私自身もそうですが、美術館に行くと、作品そのものよりも横にある解説文をじっくり読んで「わかった気になる」ことが多くあります。でも、芸術を本当に楽しむには、それとは別の視点が必要だと、本書『センスの哲学』は教えてくれました。
芸術とは「時間を味わう」こと
芸術作品は、「時間の結晶」とも言えます。
美術も、文学も、料理も──ファストに消費するのではなく、「じっくり味わう」ことで、その本質が見えてきます。
哲学者ベルクソンは、時間を「ただの経過」ではなく、「生きた流れ」として捉えました。
物理的な現象──たとえばビリヤードの球のように、原因と結果が決まっている世界では、反応は一つしかありません。けれど、生物(=私たち人間)は違います。人の反応には遅延があり、揺らぎがあり、予測できない。つまり、自由と多様性があります。この「自由」を自覚し、その余白を楽しむこと。れが、芸術を味わう態度につながっていきます。
芸術鑑賞をする場合は、「意味を探す」のではなく、「リズムを感じる」こと。意味を頭で理解するよりも、心や体に自然に浮かび上がる感覚──それを信じることが、センスを育てることにつながります。
芸術と多様性──「こうでなければ」に抗う力を養う場
人間は本質的に、偶然性や多様性を求める存在です。
さまざまな作品に触れることで、私たちは「生き方にも無数のパターンがある」ことに気づきます。
芸術とは、社会の中で「正しさ」や「善悪」が問われる以前の、人間の可能性を映し出す場です。現実から逃げるための娯楽ではなく、「現実を別の視点から捉え直す手段」なのです。つまり、「どう生きるべきか」という倫理や正義とは違う、「どう感じ、どう在るか」を探る営みなのです。
ゲームや物語もまた、「正解をすぐに求めず、迷いながら、決まらない状態を楽しむ」──そんな芸術の一種なのかもしれません。
また、AIと人間の芸術の違いは、AIはリズムや構造を模倣することはできても、「生きた身体」や「衝動」は持ち得ません。人間の芸術は、無意識や身体性に根ざした、もっと深くて曖昧なもの。だからこそ、心に触れるのです。これを時間をかけて、味わいましょう。
最後に
今回は、千葉雅也さんの『センスの哲学』からの学びを紹介しました。
本書では、センスを「直観的で総合的な判断力」と定義しています。そう考えると、私たちの人生そのものが、判断の積み重ね=センスの結晶。だからこそ、センスを育てるための「文化資本」を、惜しまず積み上げていきたいと思いました。
気づきのある1冊です。是非、あなたも読んでみて下さい。哲学っぽくなく、むしろ、俗っぽくもあり、面白いです。