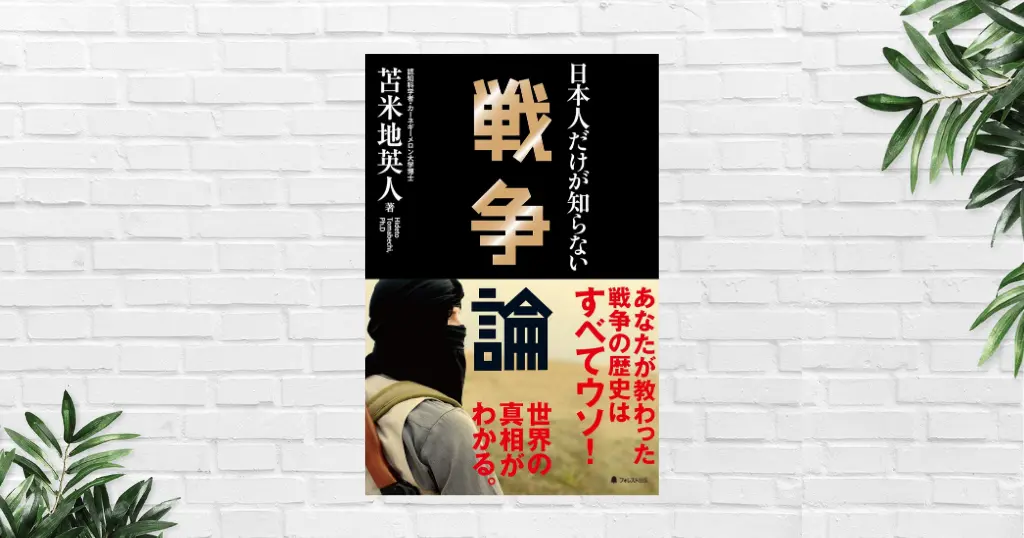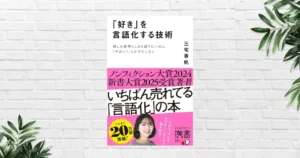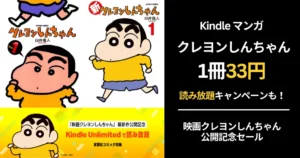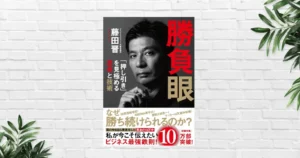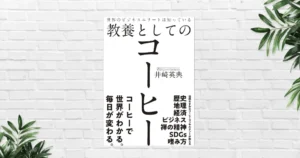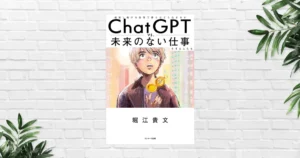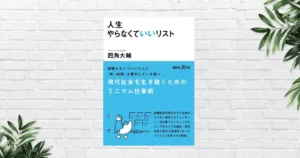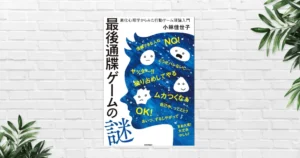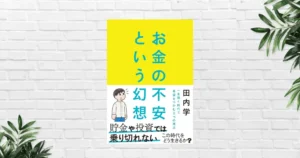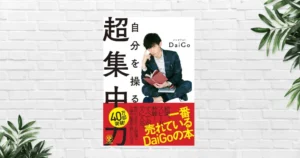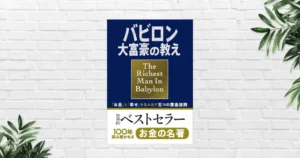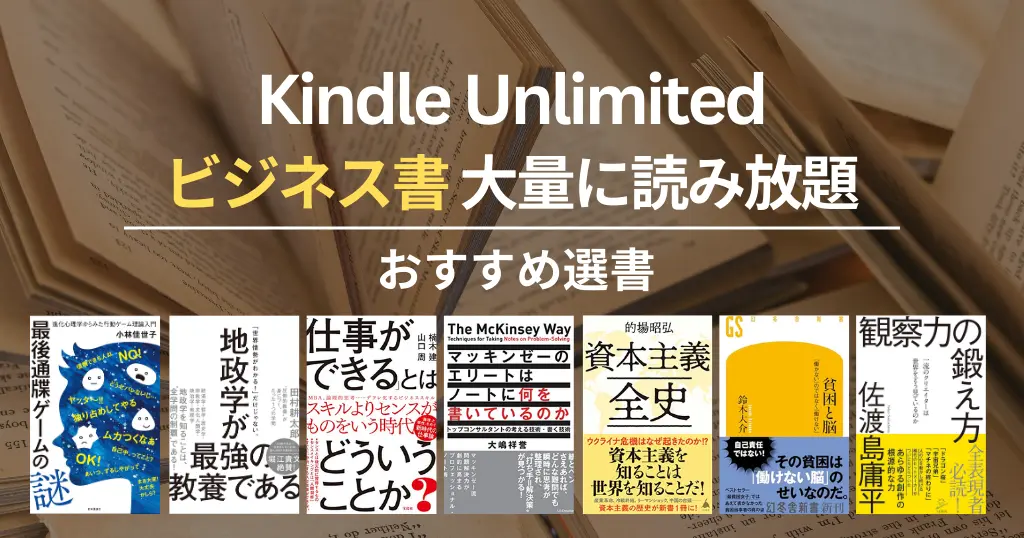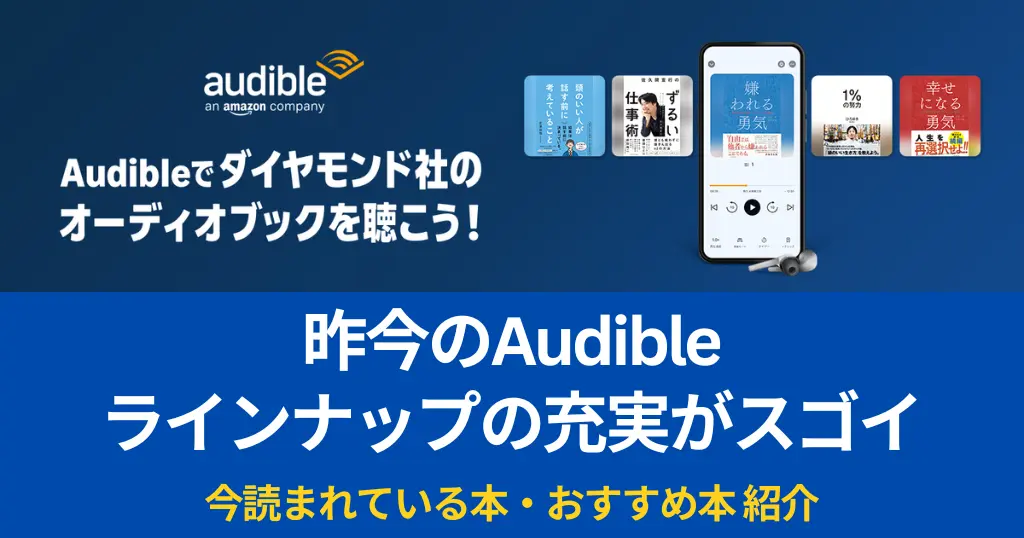- 戦争の真実。「戦争=領土争い」の裏で行われる「戦争=お金の争奪戦」
銃や爆弾ではなく、資源・通貨・情報を巡る争奪が世界を動かし、私たちの資産を左右している。 - 通貨発行権を握る者が最大の受益者
戦争は国ではなく金融資本家を潤す。国債や金利構造の裏に潜む利益の流れを暴く。 - 「誰が得をしているか」で世界が見える
国際情勢や報道の裏側を読み解き、資産と自由を守る視点を養える一冊。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『日本人だけが知らない戦争論』ってどんな本?
「戦争論」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?
武器や兵器、領土争い、歴史的な戦い――多くの人は軍事の世界を想像するでしょう。
しかし、苫米地英人さんの『日本人だけが知らない戦争論』は、、そんな固定観念を根底から覆します。
この本が描くのは、「戦争=領土争い」の裏で行われる「戦争=お金にまつわる争奪戦」です。
苫米地氏は、現代の戦争を以下のように捉えます。
- 武力衝突だけが戦争ではない
- 情報戦・経済戦・心理戦が日常的に行われている
- その裏では金融資本家が通貨発行権を握り、莫大な利益を得る構造がある
資源争奪、貿易摩擦、通貨変動、金融政策――これらはすべて、利益を得るための手段。
私たちが日々目にするニュースやSNSで囁かれる陰謀論すら、この新しい戦場の一部なのです。
もしあなたが「お金」や「資産形成」に真剣であれば、この本は世界の見え方を劇的に変える一冊となるはずです。
戦争の「建前」と「本音」

本書の中で最も鋭い指摘のひとつがこれです。
戦争の建前:宗教、安全保障、自由のため
戦争の本音:お金(利益)のため
では、その「利益」は誰の利益なのか?
国民には「自国を守るため」と説明されますが、突き詰めれば戦争は領土・資源を押さえて 利益を最大化するための行為。そして、その利益の最大受益者は国家ではなく、通貨発行権を握る大銀行家だと著者は言い切ります。
「誰の利益」が最大化されているのか?
戦争では国債が大量に発行されます。
国債を買うのは銀行や保険会社などの金融機関。国は金利を上乗せして返済するため、金融機関は莫大な利益を得ます。
さらに銀行は、預金の何倍ものお金を貸し出せる仕組み(信用創造)を持っているため、個人への金利支払いは微々たるものでも、国家への貸付から巨額の利益を生み出せます。
戦争は、通貨発行権を握る者にとって最も儲かるビジネス。そして、戦費を貸し出していた金融資本家も戦争の勝者なのです。
補足:戦争資金はどこから来るのか?
戦争にはお金が必要です。戦争に必要な資金は、歴史的にも共通する手段で調達されます。
- 増税 – 戦時税や特別税で国民から直接徴収
- 国債発行 – 政府が戦時国債を発行し、銀行・保険会社・投資家・海外金融機関から借入。
- 通貨発行 – 中央銀行が紙幣を増刷して戦費を供給(戦後インフレの要因にも)
- 海外借入 – 外国政府や国際的銀行家からの融資(政治的依存を伴う)
- 資源・物資の徴発 – 国家が強制的に物資を確保
- 占領地からの収奪 – 占領地の資源や労働力を直接利用
現代の先進国では主に国債発行と増税が中心です。表向き、「平時」と変わらない形で資金調達が行われるため、国民は戦争の負担を直接意識しにくいですが、実際は、国民には将来の税金やインフレ負担となります。
一方、国債=借金を引き受ける銀行・保険会社・大手投資家などの金融機関には、その利息が莫大な利益となって彼らの懐に流れ込みます。これが、ここに、苫米地さんが本書で指摘する「戦争は金融資本家のビジネス」の所以です。
“戦争の勝者は領土や資源を得た国だけでなく、戦費を貸し出していた金融資本家でもある“
歴史:争奪史戦争の陰に、通貨発行権をめぐる争奪史
通貨発行権は、「お金を作る権利」。「究極の権力」です。
これを握れば、無から資金を生み出し、戦争・経済・政治のすべてに影響力を持てます。
歴史を振り返ると、大きな戦争や革命の背後には通貨発行権をめぐる争いがありました。
- ピューリタン革命(1642〜1651)
王党派と議会派の対立の裏で、国王がロンドンの金融勢力と通貨発行をめぐり衝突 - フランス革命(1789〜1799)
「自由・平等・博愛」の陰で、破綻した財政と通貨発行権を誰が握るかの争い
革命後に設立されたフランス銀行は民間資本の支配下に - 南北戦争(1861〜1865)
奴隷制廃止の裏で、銀行家は高利で資金を貸し出し、巨額利益
リンカーンは銀行家の支配を嫌い、「グリーンバック紙幣」を独自発行し、銀行家の反発を招く - 第一次・第二次世界大戦
国債発行が爆発的に増え、中央銀行・民間銀行家が莫大な利息収入を確保
戦後のブレトンウッズ体制で米国とウォール街が事実上の通貨発行権を握る
そして、現代の覇者=世界最大の通貨発行権を握るは?
そう、今でも全世界の金融市場・経済を大きく左右する、あの民間機関です。重要人物には、投資銀行出身者が並びます。そして彼らは、世界を動かす大手銀行と通じています。是非、本書で確認してみて下さい。
読後の気づきー 誰が得をするのか? ニュースを見る目が変わる

この本を読むと、日々の経済ニュースや国際情勢がまったく違って見えてきます。
この出来事で、誰が利益を得ているのか―― という視点を持ち、世を見渡すことができます。
「戦争」や「紛争」も仕掛けることで得する人が必ず存在し、ニュースやSNSに流れる“陰謀論”や“愛国心をあおる発言”も本音と建前があります。鵜呑みにすると本質を見誤ります。
「誰が得をするのか?」という問いを持つことは、国内外の政策決定や経済の動きを読み解くため力を養います。そして、それは、自己資産を守ると同時に、混乱の先に資産を増やすチャンスを見出すことにもつながるはずです。
最近は、「地政学リスク」が叫ばれるようになりましたが、戦争を「国家の覇権争い」と捉えるものが多く、金融システムが生み出す収奪の構造として捉える視点は、日本ではまだ珍しいものです。本書を読む価値はそこにあると考えます。
最後に
苫米地英人さんの『日本人だけが知らない戦争論』は、知識を与えるだけでなく、認知の変革を促す一冊となりました。
著者は情報の多角的な収集を強く推奨しています。国内メディアだけでなく海外の報道や異なる立場の書籍にも触れることで、初めて全体像が見えてくるからです。本作も、今までと異なる視点を持つ1冊となるはずです。
あなたのお金と未来を守るために、そして戦争と金融の本質を理解するために、ぜひ手に取ってみてください。