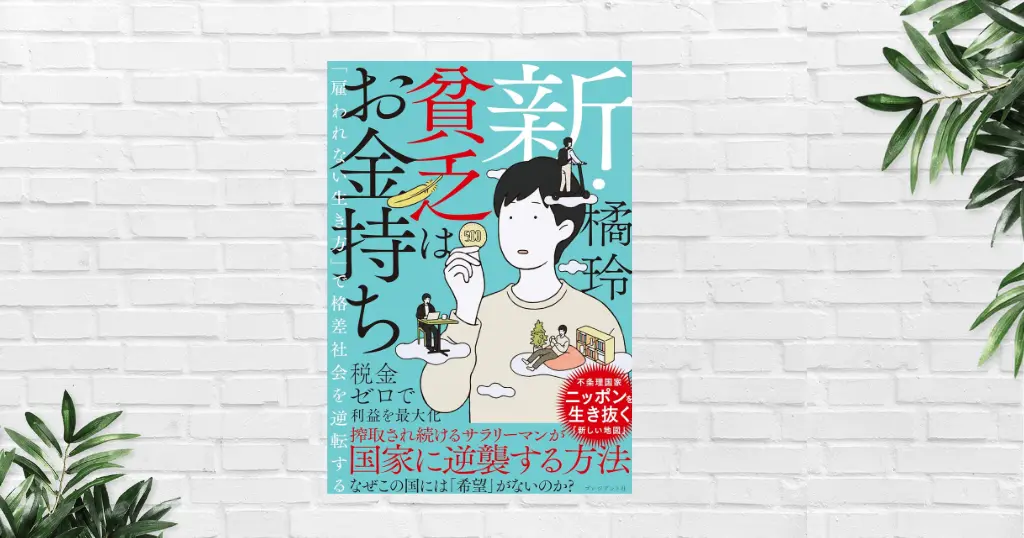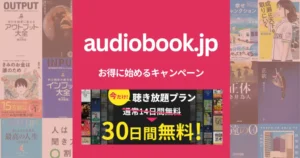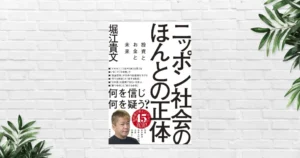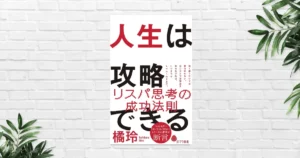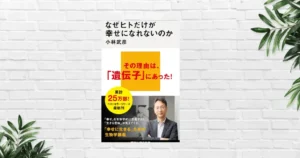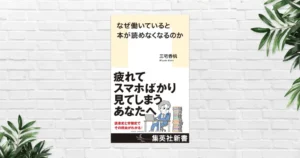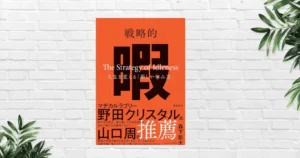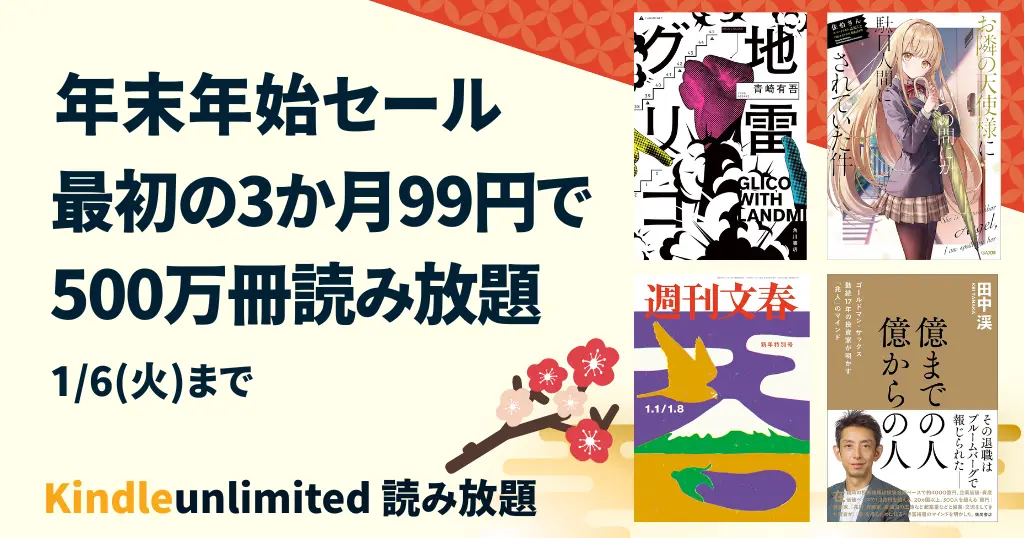- 令和版にアップデートされた「生き方の設計書」
2009年に刊行された『貧乏はお金持ち』の改訂版。16年の間に大きく変化した税制・社会保険・働き方が激変した令和の時代に対応。 - 「マイクロ法人」で格差社会を逆転する発想
個人とマイクロ法人という二つの法的人格を使い分け、所得・税・保険料を最適化する――それが橘玲流の戦略。国家を頼るのではなく、国家が作った制度を“道具”として賢く使いこなすことで、格差社会を逆転する方法を提示する。 - 知識が自由をつくる
制度を嘆くより、“ゲームのルール”を理解し、自らの戦略で動け。本書は「何を学び、どう活かせば自由を得られるのか」を示す“知的地図”。知識こそが、令和の自由を手にする最大の武器。
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『新・貧乏はお金持ち』ってどんな本?
橘玲さんの『新・貧乏はお金持ち――「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』は、2009年に刊行された『貧乏はお金持ち』の改訂版。16年の間に大きく変化した税制や社会保険制度、そして働き方のトレンドに合わせて、令和版として再構築された一冊です。
私は今回、発売当初に2009年版を読んで以来の再読です。懐かしさと新しさが入り混じる読書の中で、当時の私にはファイナンスの知識が足りず、読みこなす力がなかったことを思い出しました。
2009年といえば、世界がリーマン・ショックの余波に揺れていた時期。株式市場は暴落し、企業は雇用を削減、個人は資産を失い、将来への不安が社会を覆っていました。
そんな時代の中で読んだ本書は、「サラリーマンという安定神話が崩れつつある現実」を改めて突きつけられた一冊。「雇われない生き方」を提唱した本書は、制度の歪みを逆手に取る知的なサバイバル戦略を提示してくれました。
国家に依存するのではなく、国家を“道具”として使うという考え方は、橘さんの他の著作でも語られてきましたが、経済の混乱期だったからこそ、より多くの人の心に響いたのではないかと思うのです。
私もその一人です。
「脳が喜ぶ生き方」をモットーにしていた私にとって、「雇われない生き方」はいつか達成したい目標でした。そして今、それを実現できているのは、本書に限らず橘玲さんの一連の書籍がその思いに火をつけ、目指す方向性を示してくれたからだと確信しています。
本書のテーマ:「雇われない生き方」で格差社会を逆転する
橘玲さんが一貫して唱えるのは、「国家を頼るな、使いこなせ」です。
サラリーマンという“制度的に不利な立場”を脱し、個人が主体的に自分の人生を設計する――それが本書の核心です。
昭和の成功モデル「良い大学→大企業→定年まで雇用→年金で老後」は、もはや幻想。
その代わりに必要なのは、制度を理解し、国家の仕組みを“道具”として使いこなす知性です。
それを実践するツールとして、橘さんが提案するのが「マイクロ法人」という戦略的手段です。
「マイクロ法人」戦略とは?
「マイクロ法人」とは、個人が小規模な法人を立ち上げ、
「個人」と「法人」という二つの“(法的)人格”を使い分けて所得や税金、社会保険料を最適化する仕組みです。
この発想は単なる節税テクニックではありません。
制度の歪みを理解し、それを逆手に取る“知的サバイバル戦略”です。
たとえば、
- 法人を通じて経費計上が可能になる(支出の最適化)
- 社会保険料を自分で設計できる(社会保険料の負担軽減)
- 資金調達・経費処理・損失繰越など法人会計が活用できる(所得の最適化)
といった構造を理解し、人生全体の“収支”をデザインする考え方です。
つまり「サラリーマンというレールを外れても、制度の中で自由に生きる」ための実践的な手法なのです。
「16年で話があべこべになった」――新版で何が変わったのか?
新版のまえがきで橘さんは、2009年から2025年の時間経過を経て、「16年で話があべこべになってしまった」と語っています。
この“あべこべ”とは、当時の節税や制度活用の常識が、今では真逆になってしまったという意味です。
16年間の主な変化
- 納税戦略の逆転
旧版では「法人を赤字にして、個人で納税する」方が有利でしたが、
新版では「個人の所得を下げて、法人で納税する」方が有利に。
→ 法人税率が下がり、法人側に利益を集めた方がトータル負担が軽くなる構造に。 - 社会保険料の上昇と“ステルス増税”
社会保険料が年々上昇し、サラリーマンの手取りは減少。
「ステルス増税」によって、企業の賃上げが実質的に無効化される事態も。
一方で、自営業や法人化した個人は「報酬設計」を自分で決めることができ、柔軟に調整可能。 - 働き方の変化
副業解禁、SNSを活用した個人ビジネスの増加など、「雇われない生き方」が現実的な選択肢に。
その結果、制度を理解して行動できる人ほど、格差を逆転できる時代になったのです。
サラリーマンが不利な理由
橘さんが繰り返し強調するのは、「サラリーマンは、制度的に最も“搾取されやすい”立場にある」という事実です。
| 項目 | サラリーマン | 自営業・法人 |
|---|---|---|
| 社会保険料 | 給与に連動して強制徴収 | 所得を調整して負担を軽減できる |
| 控除の自由度 | 基本的に、給与所得控除のみ | 経費計上や法人控除が可能 |
| 給与明細 | 自動的に天引き | 自分で報酬を設計できる |
| 税・保険料の交渉力 | 節税・資産設計の自由度がない | 節税・最適化の余地あり |
政府は“増税”とは言わず、社会保険料や支援金の名目で負担を増やす「ステルス増税」を進めています。
その最大の犠牲者が、サラリーマンなのです。
確かに、サラリーマンは社会保障や税について勉強せず、無知であっても、退職するまでは問題なく生計を立てることはできます。しかし、退職して誰も税金計算・社会保障の支払いをしてくれなくなったとき、その支払額に驚愕することになるのです。
「雇われない生き方」に必要な6つの金融知識
橘さんの主張を現実化するには、「国家を使いこなす知識」が必要です。
『新・貧乏はお金持ち』はその“入口”。金融知識を網羅した教科書ではありません。
「なぜそれらを学ぶ必要があるのか」「学ぶことで何が可能になるのか」を教えてくれる“地図”のような存在です。
私自身の学びのためにも、雇われない人生に必要な金融知識を以下の6分野に整理してみました。
| 分野 | 項目 | 必要な知識 |
|---|---|---|
| 1️⃣ 会計 | 損益計算書 経費 帳簿付け | • 損益計算書と貸借対照表の読み方 • 収益・費用・資産・負債の概念理解 • マイクロ法人の帳簿付けや経費計上の判断に必要 |
| 2️⃣ 税務 | 所得税 法人税 控除・節税 | • 所得税・法人税・住民税・事業税の違いと仕組み • 給与所得 vs 事業所得 vs 配当所得の税率 • 控除・経費・青色申告など節税に関する知識 |
| 3️⃣ 社会保険 | 保険料の仕組み 負担構造 | • 厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険の仕組み • サラリーマンと自営業者(国民健康保険・国民年金)の負担差 • ステルス増税への対応力 |
| 4️⃣ 法人運営 | 設立手順 報酬設計 資金管理 | • マイクロ法人の設立手順(定款、登記、銀行口座開設など) • 役員報酬の設定と分配の考え方 • 法人と個人の資金の分離管理 |
| 5️⃣ 資産運用 | 投資商品 リスク管理 複利 | • 投資信託・株式・債券・不動産などの基本的な金融商品 • リスク分散・長期投資・複利効果の理解 • 法人を通じた資産形成(法人名義の証券口座など) |
| 6️⃣ ファイナンス | 資本コスト 資金調達 自由設計 | • 資本コスト・キャッシュフロー・レバレッジなどの概念 • 資金調達(融資・補助金・クラウドファンディング)の選択肢 • 「お金を稼ぐ」だけでなく「お金を使って自由を得る」発想 |
総括:令和の「自由への設計図」
『新・貧乏はお金持ち』は、単なる節税本でも、稼ぐための本 でもありません。
国家・会社・税制という巨大なシステムの中で、「個人がどのように自由を獲得するか」を考えるための案内図です。
新版では「変化した制度の中で生き抜く力」を教えてくれます。
橘玲さんが描く「雇われない生き方」は、不安定な時代における“自由の再定義”そのもの。
読後、あなたもきっと思うはずです。「貧乏」とは、収入の多寡ではなく、“知らないこと”なのだ――と。
1/29まで:いつでも解約可能