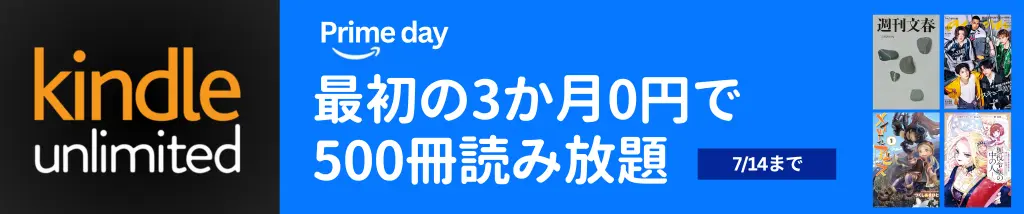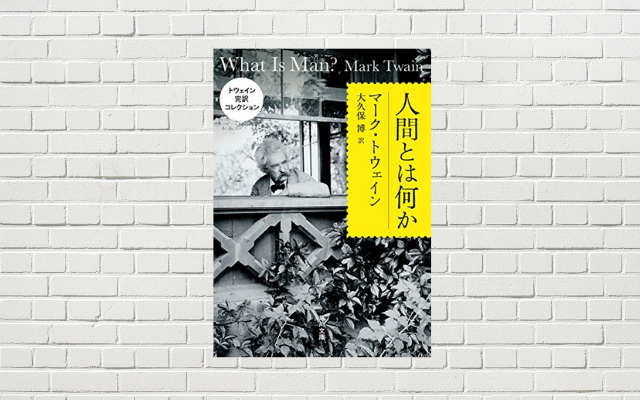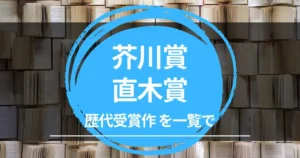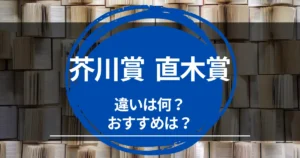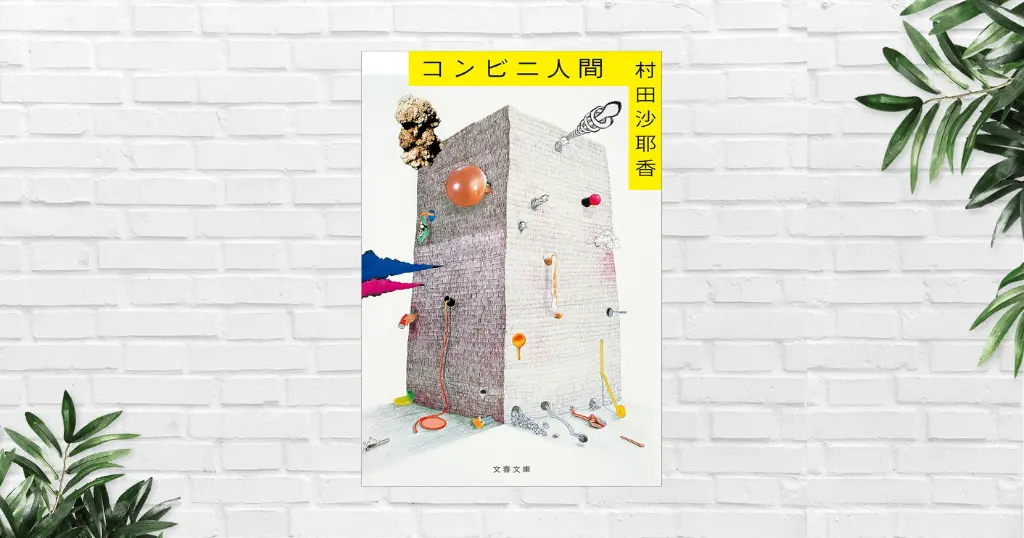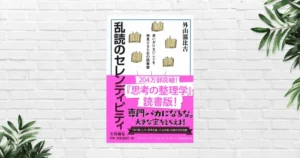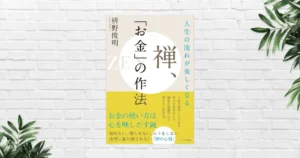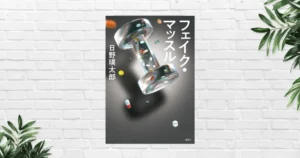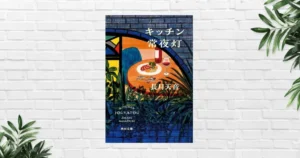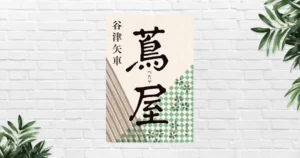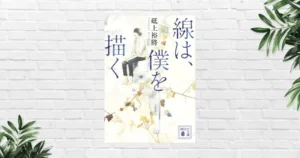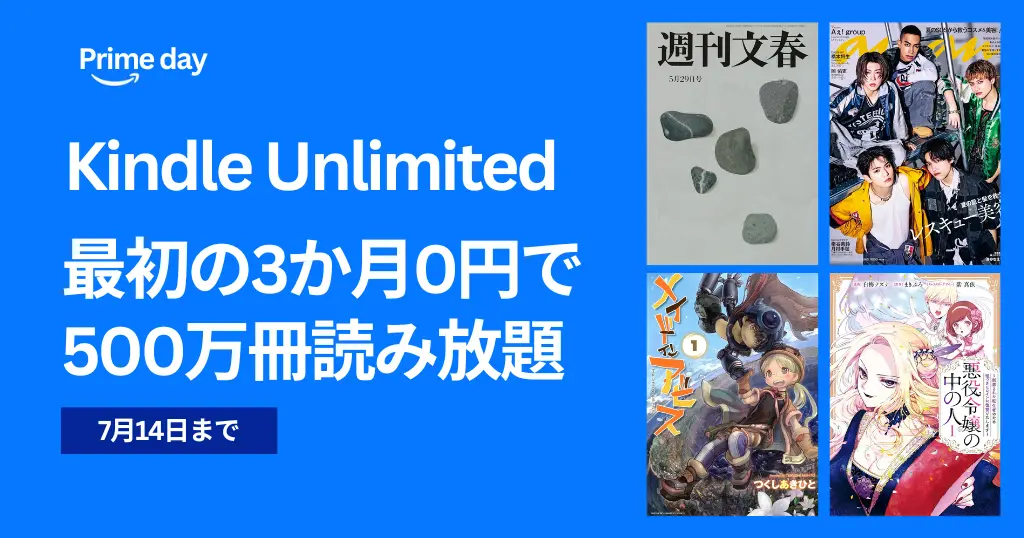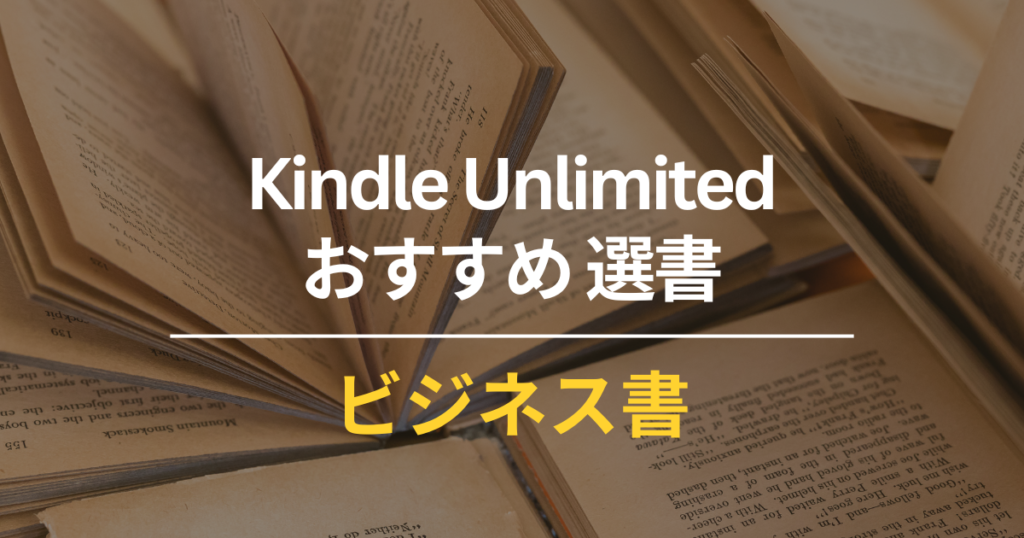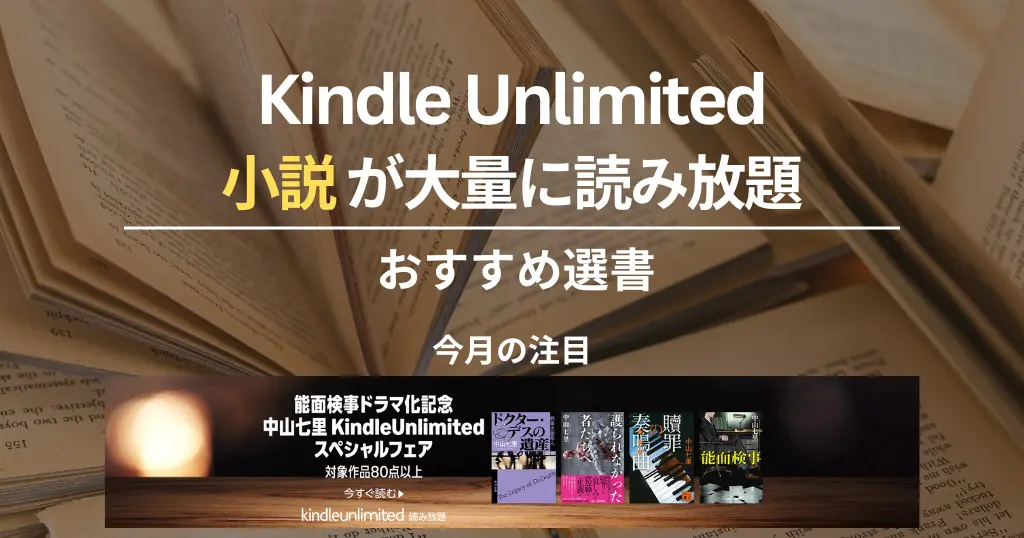- はたから見れば一人に見える結合双生児の姉妹・杏と瞬。その姉妹の父も、胎児内胎児として、兄の身体から取り出されて生をを受けた稀有な生い立ちを持つ。父の片割れともいえる伯父の死からの49日間を描く
- 片方が思考を失ってしまったら、一体どうなるのだろうかー
私とはいったい何で、人は死ぬとどうなるのかー
伯父の死をきっかけに、姉妹は「自己」「意識」「死」を深く考えざるを得なくなる - 第171回芥川賞の受賞作。読書に多くを考えさせる深い作品。哲学的。私は好き
★★★★☆ Audible聴き放題対象本
『サンショウウオの四十九日』ってどんな本?
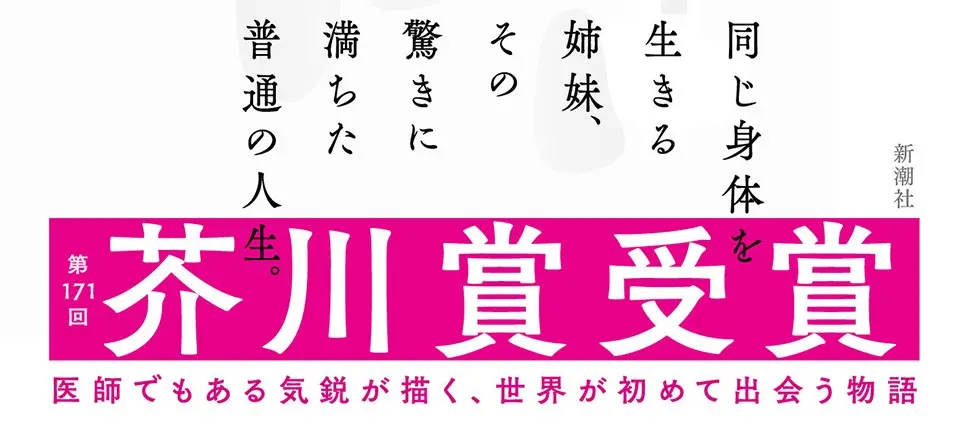
私とはいったい何で、人は死ぬとどうなるのかー
『サンショウウオの四十九日』は、第171回芥川賞の受賞作。
主人公は、29歳の双子の姉妹・杏(あん、わたし)と瞬(しゅん、私)。はたから見れば一人に見える結合双生児。身体一体に「わたし」と「私」という2つの意識を持つ稀有な存在。そんな姉妹の伯父が亡くなってからの四十九日間を描きます。
実は、姉妹の父も特異な双子。父は、双子の兄である伯父の体内に宿って生まれた「胎児内胎児」。しかも、もう一人は兄の体内で亡くなり、吸収されたという。父は幸いにも、兄の体内から分離され、「個」として人生を歩むことができました。しかも、兄のように病気がちな人生を歩むこともなく元気に…
伯父の死で、「意識一つに身体一体」なら心臓が止まれば死ぬ、という当たり前の事実を突きつけられた姉妹。
片方が思考を失ってしまったら、一体どうなるのだろうかー
一つの身体に二つの意識がある姉妹は、自分たちの「死」を突きつけられるのです。
著者の朝比奈秋さんは、医師 兼 作家。これまでも、『植物少女』で三島賞、『あなたの燃える左手で』で野間文芸新人賞を受賞するなど、実力派。結合双生児は著者の想像です。しかし、医学的知識のもと構成されているので、まるで現実の奇病であるかのように話が進行します。
本作は、結合双生児の話ではありますが、姉妹の抱える問題は、現代の「自己同一性障害」や「認知症」、さらには、我々が日常生活の中で感じる「私とは何か」という哲学的な問いに深く通じており、全くの他人事ととして読むことはできません。
本書は、読者に「自己」「意識」とは何かを問うてきます。そして、一方で「他者との関係・関わり方」についても考えさせます。読者にモノを問う芥川賞らしい小説です。
考える読書が好き方におすすめです。ちなみに私は「二度読み」しました。
- 深く考える文学作品が好きな方
- 「自己同一性」「自他の境界」など、「自己」を問う作品に関心のある方
- 人の人生を描く作品が好きな方
『サンショウウオの四十九日』あらすじ
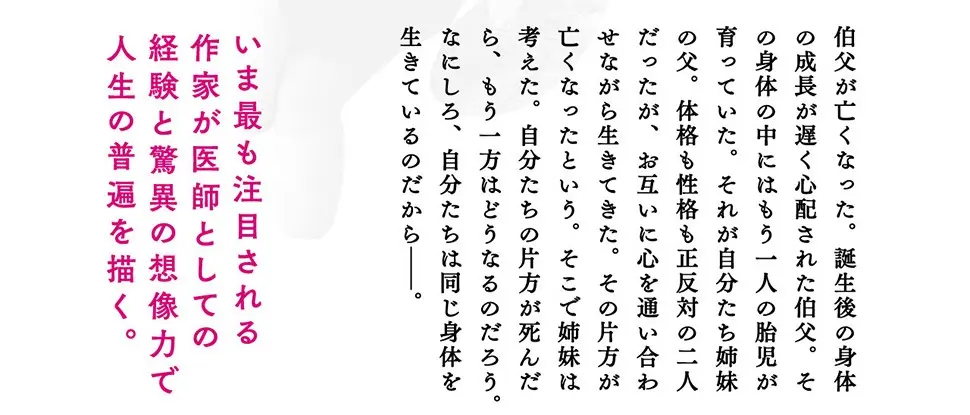
私たちは、全てがくっついていた。顔面も、違う半顔が真っ二つになって少しずれてくっついている。結合双生児といっても、頭も胸も腹もすべてがくっついて生まれたから、はたから見れば一人に見える。(中略)特異な顔貌をした「障がい者」だとみられる。
歪んだ顔面たち、かわりに入れ替わる二つの声色、時に別々に動く左右の目
意識自体は繋がっていなくても、一つの体で思考も感情も感覚も共有し、それらが意識と意識の間に介在していた
『サンショウウオの四十九日』あらすじ ※ネタバレ含む
周りからは一人に見える姉妹。でも、すぐ隣りには別のわたしがいることを、当たり前のこととして育った姉妹。
そんな、一つの体を共有して生まれてきた姉妹が、「結合双生児」だと診断を受けたのは5歳のこと。両親にとっても驚愕の事実。それまでは、左右の歪みから、障がいがあるのかも… と見られることはあっても、「一人の人間」と扱われて育ちました。
29歳にして直面した「伯父の死」。生前中、ほとんど接することはなかったものの、「兄が死んでも父は生きている」という当たり前の現実に、姉妹は、「意識」と「死」について、考えさせられることになるのです。そして、若かりし頃の出来事を回想するのです。
- 1つの身体に2人が存在するとわかって、改めて出生届を提出
- 行政的に、別の「個」として認められる
- 両親は、「存在」を気づいてあげられなかった、瞬に対してひけ目を感じている
- 一行ごとに二人で手紙を書く文通のやり取り
- 姿が見えない相手から、「わたし」と「私」はどのように受け止められるのかの実験
- 文通相手に「結合双生児」の姿を想像して描いてもらうと、顔は一つと言っているにも関わらず、必ず二つの頭がある人のイラストを描いてくる
- 高校の郊外学習で出向いた博物館で説明を受けた、陰陽図(別名:陰陽魚)
- 白と黒の勾玉が、互いを追いかけ、影響を与え合い、一つとして存在している姿に、杏は自分たちを重ねる
- この授業で同僚が放った言葉「じゃあさ、おまえらも片っぽ死んだら両方死ぬん?」
- この言葉が、本作を貫くテーマとなる
このような出来事を思い出しながら、「自分の意識」「二人の死」について、49日間、考え続けるのです。

「サンショウウオの四十九日」の主な登場人物
本作の登場人物はあまり多くはありません。4人の関係性を理解すれば、スムーズに読めます。
| 濱岸杏(あん) | 結合双生児の姉妹。左半身。「私」 |
|---|---|
| 濱岸瞬(しゅん) | 結合双生児の姉妹。右半身。「わたし」 |
| 濱岸若彦 | 杏と瞬の父。兄・若彦の胎児内胎児として生まれる |
| 勝彦 | 杏と瞬の伯父。若彦の兄。大学教授。「勝彦の死」が物語のスタート |
『サンショウウオの四十九日』感想・考察

なぜ、サンショウウオなのか?
私の中に瞬が生まれて、瞬の中に私が生まれる、それがどういうことなのかを考えるたびに頭の中でサンショウウオが育っていった。私が黒サンショウウオで瞬が白サンショウウオ。くるくる回れば一つになる、二人で一つの陰陽魚
陰陽図の黒と白の勾玉が重なり合う姿は、別名「陰陽魚」とも呼ばれると博物館で説明を受けた杏。しかし、杏は、魚ではなくサンショウウオに見えたという。サンショウウオは、イラストのような4本足のある爬虫類です。
この陰陽図にある、黒と白の点も重要な意味を持ちます。これは、まさに、胎児内胎児として生まれた父・伯父の関係をも表すからです。
なぜ、魚ではなく、サンショウウオなのかー
タイトルになるぐらいだから、本作にとって非常に重要ポイントのはずです。しかし、作品内ではその理由をわかりやすく説明してはいません。そこで、サンショウウオについて、複数のサイトで調べてみると以下のような記載が。
- オオサンショウウオは、日本固有のサンショウウオ
- 国の天然記念物。絶滅危惧種として環境省のレッドリストにも指定
- オオサンショウウオは、身体を半分に裂かれても生きていることから「ハンザキ」とも呼ばれる
- 見た目はちょっと不気味
- 孵化した当初は足も生えていないが、しばらくすると足が生え外鰓が消えて変態して幼体となり成体となる
- 幼生時はえら呼吸。成体は肺呼吸と皮膚呼吸
「天然記念物」「身体を半分に裂かれても生きている」「変態生物」といったところが、「杏と瞬」、「父と伯父」の姿に重なります。
近くても交わらない「意識」
本作で深く描かれているのは、杏と瞬が一つの体を共有しながらも、「意識」や「記憶」はそれぞれ存在している点です。2つの意識は、影響を与え合うことはあっても、完全には混じり合わない、つまり、普通の人より隔てる膜は薄いながらも自他を分ける「境界」があるのです。
これは、どれだけ近くにいても、身体・顔が一つであっても、他者は他者であり、完全に理解し合うことはできないという事実を象徴しています。本作でも杏と瞬は、時折、相手が考えていることがわからなくなる姿も描かれます。
しかし、それでも、彼女たちは互いに支え合いながら生きています。特に病気になったり、相手が弱っている時、そっと助けを出すのです。
自他の境界
意識はすべての臓器から独立している―。しかし、1つの意識で1つの体を独占している人たちにはそれがわからない。思考は自分で、気持ちも自分、体もその感覚も自分そのものであると勘違いしている。自分の気持ちが一番大切、なんていう言葉を聞くたびにニヤニヤと含み笑いをしてしまう。(略)
自分の身体は他人のものでは決してないが、同じくらい自分のものでもない。思考も記憶も感情もそうだ。そんな当然のことが、単生児たちには自分の体で持って体験できないから、わからない。
みんなくっついて、みんなこんがらがってる。(中略)いろんなものを共有しあっていて、独占できるものなどひとつもない。他の人たちと違うのは、私と瞬はあまりに直接的、という点だけだった。
人は「自己」を意識したとき、「他人」との間に境界を引きたがります。しかし、みんな、絡まり共有し合っている。「人との関わり合い」について考えさせられるフレーズです。
そもそも自他を分ける考えの一つとも言える「自分の考え」も、実際はもともとは他者の意見がもとになっています。簡単なところでは、好意を持つAさんが「〇〇が好き」と聞いて、自分も「〇〇」が好きになるというのも、「感情」が自分オリジナルでないことを示す一つです。思考も記憶、歴史ですら、人の意見で見方が変わってしまいます。
『人間とは何か』で著者のマーク・トゥエインは、「自分にオリジナルなものなどない」と「人間の本質」を述べています。
人間(の心)も動物(の心)も機械だ。人間にも動物にも真にオリジナルな物など作れはしない、すべては昔からのコピーの累積だ。人間が自由意志と錯覚しているものは自由選択に過ぎない。人間の行動の根本原理は自己満足である。 『人間とは何か』より
『人間とは何か』価値観を変えさせられる刺激的な良書です。
「意識」と「死」
死んでも、意識は続く。死が主観的に体験できない客観的な事実で、本当に恐るべきは肉体の死ではなく意識の死ならば、どういったことで意識は死を迎えるだろうか。大きな疑問が込み上がってくる。
意識はなんなのか。私とは違うものなのか。
死んでも続く意識を絶命に至らしめるものはなんなのか。
すると、巨大な穴に落ちるような感覚が起こって私は思わず胸元に本を引き寄せた。
本書を貫くのは「自己とは何か」というテーマです。上記フレーズも、非常に哲学的です。「意識」とは何か? 「死」とはどういう状態なのか?を考えさせられます。
意識はすべての臓器から独立している。もちろん、脳からも。故に、死んでも、意識は続く。
デカルトの「我思う、故に我あり」に通ずる難解な問いに、頭がしびれます…
しかし、一歩引いて考えてみる。私たちは、死んだら肉体は滅び、脳も滅びることを理解しています。しかし、一方で、死んでも「意識」は消えないと思っているところがある。仏教では死んだら極楽浄土か地獄に行くと教え、死んでから49日目は、どちらに行くかの審判の日であったりするわけです。これは、「死んでも、意識は続いている」状態と解釈できます。
物語理の中で、瞬は、別の形で、生きている杏の傍らで、自分だけが死んでしまったのではないかという体験をします。意識はあるのに、全く身体を感じられない感覚を味わうのです。
そして、その時、瞬は、まだ、自分が一人の人間(意識)として見出されていなかった幼児の時のことを思い出します。それは、杏の中にあって、自分の意識では身体を動かせなかったときのこと。杏が眠りについた後、だけ、少し自分の意識で身体を動かすことができた経験です。そして、布団の中で瞬自身の意識で身体を動かし、おばあちゃんにちょっかいを出し、ぎゅっと抱きしめられたことを思い出すのです。
つまり、瞬は、「意識と身体が接続されている」と実感できたときに「生」を感じ、その逆、接続が途切れた時に「死」を感じたのです。これこそが、「死んでも続く意識を絶命に至らしめるもの」に当たるのだろうか…
う~ん。なかなか解釈が難しいですが、現代科学をもってしても「死」は解明されていません。私たちは「死にゆく過程」は主観的に体験できても、「死」を主観的に体験することはできないのですから。
最後に
今回は、朝比奈秋さんの『サンショウウオの四十九日』のあらすじと感想を紹介しました。
正直、二度読みしても、まだ、スッキリ読みこなせたとは思えません。しかし、現代科学をもってしても、「死」「意識」は解明できていないので、スッキリ読みこなせなくても当たり前かなと思います。スッキリしなくても、私にとっては、いろんなことを考えさせてくれる深い読書体験となりました。また、時間をおいて再読してみたい本となりました。
合わせて読みたい2冊
本書を読了し、死について考えながら、頭に思い出したの本は、田坂広志さんの本『死は存在しない』。最新の量子力学的に死を仮説検証する本なのですが、ここでは、量子力学的に、肉体は滅んでも「意識的なもの」は存在し続けます。私が、過去に読んだ本の中で、最も説得力のあった「死後の世界」の本であり、刺激的で人生観が変わります。
もう一冊は、69回芥川賞受賞作の『ハンチバック』。こちらは、身体に障害を持つ著者・市川沙央さんが、障害者目線から「健常者が持つ特権」や「生きること」をえぐるように書いた作品です。こちらも、生きることにハンディキャップを持つ主人公がテーマ。全くテイストが異なりますが、こちらの作品も多くを考えさせます。
芥川賞受賞作を読んでみたい方
その他の芥川賞受賞作を読んでみたい方は、以下もご確認を!
-

【書評/要約】コンビニ人間(村田 沙耶香) 「普通」を押し付ける社会の息苦しさを身近なコンビニを舞台に軽やかに描く。芥川賞受賞のベストセラー
-



【書評/感想】少年と犬(馳星周) 岩手から熊本まで、犬はなぜ3000kmを旅したのかー。涙なしでは読めない感動作。芥川賞受賞作。2025年3月映画公開
-



【書評/要約】ブラックボックス(砂川文次) 「ちゃんと」と「暴発的暴力衝動」。人・世の暗部を描く、芥川賞受賞作
-


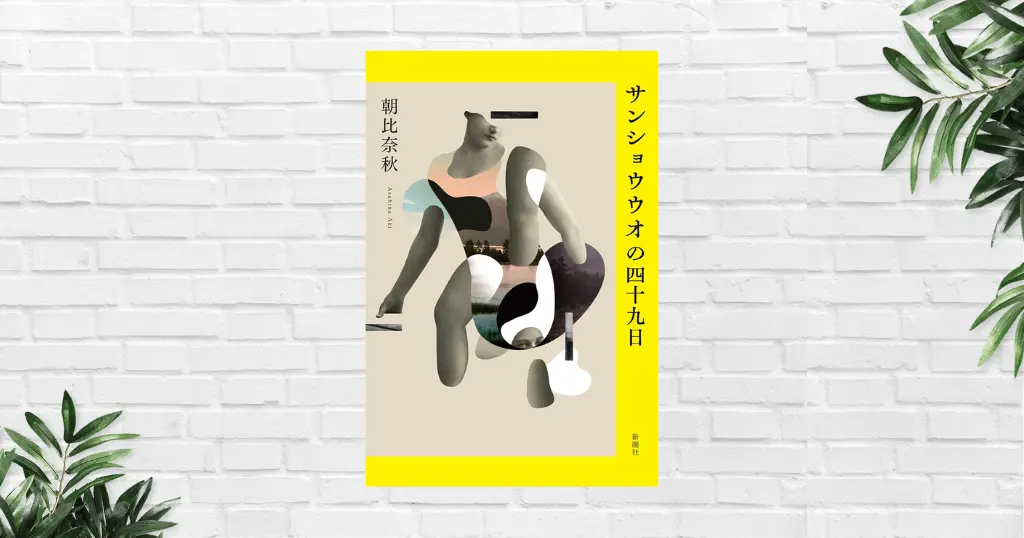
【書評/要約】サンショウウオの四十九日(朝比奈秋) 1つの身体に2つの意識。結合双生児の姉妹を描く、意識・自己・死を深く考えさせる 芥川賞受賞作
-


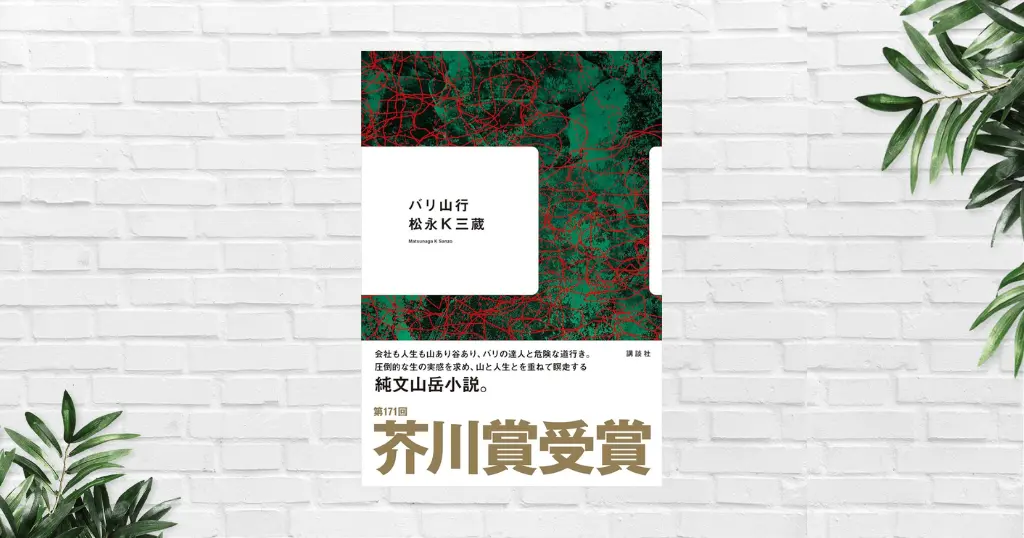
【書評/感想】バリ山行(松永K三蔵) 道なき道を自己判断・自己責任で進む同僚に何を思うー “人生”と”登山”を重ねる純文山岳文学の傑作。芥川賞受賞作
-


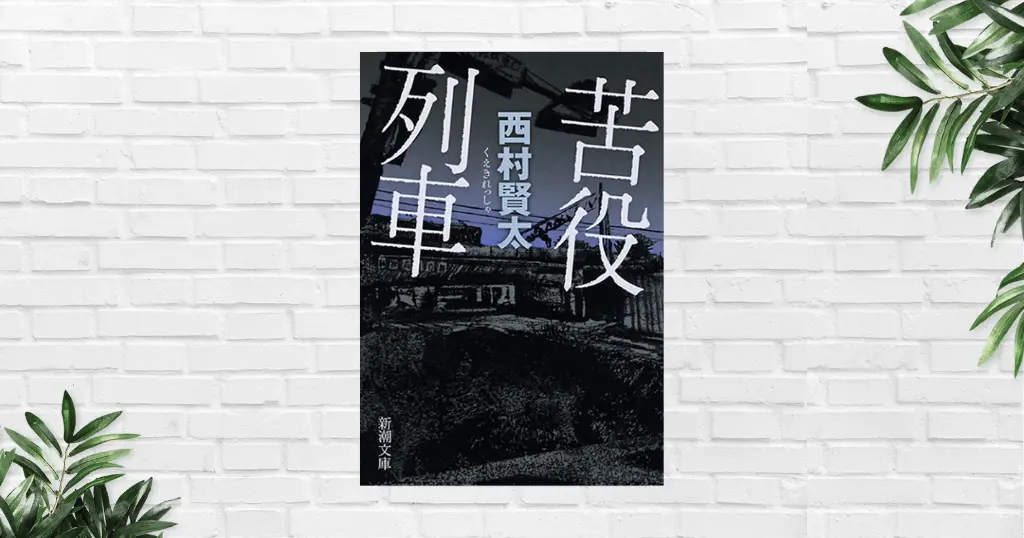
【書評/感想】苦役列車(西村賢太) 自堕落・自業自得な”クズ人生”が ヒリつくほど生々しい私小説。芥川賞受賞作